14・電影少年
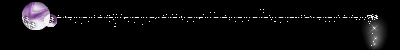
パチッ、と携帯電話を閉じる音に、二人は彼を振り返った。
「向こうも、先方で夕食を一緒に取ってからホテルに戻るそうだ」
「オーケー。じゃ、行こうぜ」
すかさずディアッカがエレカの扉を開ける。彼がハンドルを握り、助手席にイザークが、後部座席にアスランが座った。
ニコルの命日。お墓参りを終えた三人は、そのまま連れ立ってレストランへ向かった。
当初アスランは、共にプラントに来て今は別行動中のマリューやムウと合流してから、三人でホテルに戻って夕食を取るつもりだったのだが、
折角だからメシでもどう、というディアッカの提案に、二人と連絡を取ったのである。
マリュー達はグラディス艦長の遺言を守るべく、彼女の息子に会いに行った。その先で共に夕食をと勧められ、向こうもアスランに連絡を
取ろうとしていたところだったらしい。
「あいつは、連れて来なかったのか」
注文を済ませてウェイトレスが下がったところで、イザークがそう切り出した。
「あいつ?」
「フリーダムだ」
何故わからん、という様子で眉間にシワを寄せる。そんなイザークのリアクションに、アスランとディアッカは顔を見合わせて笑ってしまう。
「フリーダムって…。名前で呼べばいいだろ、普通に」
「そーそー」
「煩いっ、笑うな! 誰のことだかわかればそれでいいだろう!」
「だったら同じ理屈で、名前で呼んでも別にいいんじゃないのか?」
「なんで貴様はいちいちそういうどうでもいいことを、…ええい、とにかく! …ニコルの…ブリッツのパイロットの墓参りに行くとは、
伝えてないのか」
いくら言っても堂々巡りになると思ったのか、それとも声量が上がってきたことを気にしたのか、イザークは話題を元に戻した。
「………言ってあるし…言わなくても、キラは分かってるよ」
「それなら尚更だ。何故あいつは来ない」
「…」
微笑の消えたアスランの表情。視線がイザークの目から逸れて、テーブルの上へ落とされる。
「…イザーク、お前さ………ひょっとして」
「おい、勘違いするな。オレは別に、あいつを責めているわけじゃない」
まだキラにわだかまりがあるのか、と含ませたディアッカの問いかけに、イザークは首を横に振るかわりにギロリと睨みつけて否定を返す。
「あいつの性格からして、ニコルに会ってみたいと言い出すんじゃないかと思った。だから、お前と同行していないのが少し意外だっただけだ」
イザークの言葉に、アスランは複雑な微笑を返す。
「……言ってたよ。似たようなことは。…いつか、墓前に立たせてもらってもいいか、って。…もう少し落ち着いて、プラントからオーブに
日帰りできるようになれば、命日に来られると思う」
「日帰り?」
なんでとんぼ返りする必要がある、と訝しむイザーク。
ディアッカの複雑な視線を感じて目を上げたアスランは、彼もそれを忘れていない事を知って、自嘲するように小さな笑みを浮かべた。
「…今日がニコルの命日………。…ということは、つまり…明日はキラの友達の命日だ。…俺が殺した、キラの仲間の…」
あの時、自分が無造作に討った、キラが死に物狂いで必死に守ってきた友人。
今日自分がニコルの墓前に立ったように、明日はキラがその友の墓前に立つ。
少し目を見開いて驚いた後、「そうか」と答えたイザーク。彼がそのままこの話題を続けることはなかった。
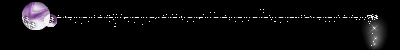
二人と別れてホテルに戻ると、マリューとムウはロビーにあるティールームで食後のコーヒーを楽しんでいた。
「お帰りなさい、アスランくん」
「ディアッカのヤツ、元気してたか」
「ええ。二人とも相変わらずで」
どうやら彼らも今しがた戻って来たところらしい。二人の前のカップにはコーヒーがなみなみと注がれており、独特の香りとともに
湯気が立ち昇っている。
どちらにしろすぐに部屋に戻らなくてはならない用事があるわけでもない。少し話をしていこうと決めたアスランは空いている席に腰を
下ろし、自分もコーヒーを注文した。
「ムウさんが記憶を取り戻したこと伝えたら、喜んでましたよ、ディアッカ」
「ハハハ。まず、生きてたってとこに驚いてたんじゃない?」
「ええ、まあ」
「私達も、久しぶりに会えれば良かったんだけど。忙しいんでしょう? ジュール隊長も、ディアッカくんも」
「そうですね。明日もまた早くから仕事があると言っていました」
「そう…」
懐かしい二人の顔を思い出したのか、それともテレビで見たラクスを守りながら評議会入りする二人の様子を思い浮かべたのか。
マリューはまるで弟の活躍を聞く姉のように穏やかに微笑んだ。
「結局アイツ、お嬢ちゃんとはどうなってるんだろうな」
「ミリアリアさんとディアッカくん? さあ…、彼女は振っちゃったって言ってたけど…実際どうなのかしら。…ふふっ、帰ったら彼女の
ほうに聞いてみましょうか」
クスクス笑いながらコーヒーを一口。それから、うーん、と視線を天井へ。
「…いやね、大分バルトフェルド隊長に毒されちゃったみたい。普通のじゃ満足できない体になっちゃった」
意味深な言い回しに、うぐっ、とムウがコーヒーを吹きかける。
カップをソーサーに戻して、じとっとマリューを睨むムウ。だがマリューは余裕の表情で微笑んだ。
「あら、なあに? コーヒーの話よ?」
「っ、…怪しげな言い方するからだろ」
嬉しそうに笑うマリューに、しまった引っかかったか、と笑うムウ。アスランも二人のやりとりを微笑んで見守りながら、運ばれて来た
コーヒーカップに口をつける。
「そうだ。メイリンさん達とは会ったの?」
ひとしきりムウをからかって満足したのか、今度は話題をこっちへ振ってきた。
「いえ。帰りに合流したいとメールがあったので、帰りの便の時間を連絡しておきましたが…今日はあちらも、家族水入らずのようなので」
「なんだ、あのツインテールのお嬢ちゃんはこっちに戻るんじゃないのか?」
「ご両親からも、随分戻ってくるように説得されたらしいですけどね。やっぱり、ちょっと…どうしてもまだ、怖いんだそうです」
「…ザフトが?」
マリューの問いに、頷くアスラン。
議長の理想世界にとっては不必要と、アスランもろともに切り捨てられたメイリン。自分が忠誠を誓い属していた組織に裏切られ、
仲間と信じてきた相手に殺されかけた事実は、彼女の心に大きな傷を残した。彼女はずっとそのザフトの制服を着続けていたが、いつか
戻れる日に希望を繋いでのことではなかったようだ。
メイリンの冤罪が証明されたと迎えにきた姉に、彼女は「両親には会いたいが、自分はこのままオーブに残る」ときっぱり言い切ったのである。
「しかしなぁ、別に軍に戻らなくてもいいから、家族の側に居たほうがいいんじゃないのか? あんな事があったんなら、特にご両親は
心配だろう。…まだ十四、五だろ? 彼女」
「プラントでは、もう立派な大人ですよ。それに、もうオーブ政府の空港管制オペレーターの仕事が決まったそうですから」
「そうね。これを機にお姉さんから自立したい、とも言っていたものね」
「ルナマリアのほうも、これを機に妹離れしなきゃ、なんて言ってましたよ」
「…いい姉妹じゃないの」
しみじみとムウが呟き、大分冷めてきたコーヒーを一口。
自立、妹離れ。一見すると距離を作るかのような単語だが、相手への思いやりと冷静に自分を見つめる目がなければ、なかなか言い出す
ことも出来ないことだ。
メイリンとルナマリアのことには触れても、カガリのことには触れない。
イザークとディアッカのことには触れても、ニコルのことには触れない。
あれこれ話題を作りながら、今日訪れて来た相手のことには触れない。
巧みに会話の流れをリードするマリューは、世間話というものを心得ている。傷であろう部分には触れないように気を遣いながら、
けれど同時にその傷が傷痕になって完全に塞がっているかどうかも、そっと確かめているようだ。
塞がった傷痕をいつまでも庇ってばかりでは、その部分は弱ったままになってしまう。かと言って無理に弄れば、別の傷がついたり
傷口がまた開いてしまったり。
だから、その押し引き加減を誰もが気遣う。当たり前の思いやりとして。
そうしてやはり、キラのことも話題には出されなかった。
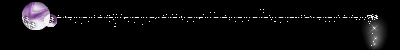
――――君も…トールを殺した…。
一人の部屋に戻って静寂に満たされると、途端にその声が耳の奥で甦った。
――――でも君も、トールのこと知らない。…殺したかったわけでも、ないだろ?
勿論、そのトールという少年を殺したくて殺したのではない。
…けれど、それよりももっと悪い。
あの時アスランは、あの戦闘機を『敵』とすら認識していなかった。
キラとの戦いを邪魔する、『邪魔なモノ』、でしかなかった。
ただ無造作に払った………耳元を煩わせる虫を咄嗟に払うのと同じに。
同じ咄嗟のことでも、キラは自分の命を守ろうとした結果だ。そこにニコルを殺そうとする意志はなかった。だが自分は、『トール』
を殺そうという意志はなくとも、『それ』を排除しようとする明確な意思があった。邪魔だというだけで…『敵だから』という大義名分も
なく、ただ邪魔だからという傲慢な動機で、彼の命を屠ったのだ。
劣等感と罪悪感が、静寂によって倍増されてゆく。
このままこの部屋でじっとしていたら、押し潰されてしまいそうだ。今更押し潰されたところで、誰一人戻って来ることはないというのに。
何を考えても、ネガティブなほうにしか行かない。
シャワーを浴びて寝てしまおう。アスランはそう決めて、座り込んでいたベッドから立ち上がる。
まるでそのタイミングを見計らったかのように、携帯電話が鳴り始めた。
そういえば、無造作にハンガーに掛けたジャケットのポケットへ入れっぱなしだった。取り出すと、発信者はなんと、キラと表示されている。
「もしもし」
『あ、アスラン』
優しい声が耳元で響く。クス、と微笑んだ気配さえ伝わってくるようだ。
『ごめんね、そっちもう夜中でしょ?』
「いや、…うん、まあ」
『話して大丈夫?』
「ああ、勿論」
再びベッドへ腰掛けて、目を閉じる。微笑んだキラの顔が、すぐ間近にあるかのように感じた。
『………』
だが、それきりキラは言葉を繋ごうとしない。
「…どうした?」
『あ、うん。……ごめん、用事があったわけじゃないんだ、実は。なんか…、声、聞きたくて』
「…」
今度はこちらが言葉を失う番。
せりあがってきた感動を止めるように、口元を手で覆った。
『ご、ごめんね。ヘンなこと言い出して。ただ、…その…何て言うか』
「俺も、キラの声が聞きたいと思ってた」
『………え、ほんと…?』
「ああ」
二年前、ジャスティスに乗ってオーブに降りた時にも。デュランダル議長の目指す世界と決別し、再びアークエンジェルに乗り込んだ時にも。
いつだって、ぐるぐると不毛な迷路へ思考回路が迷い込んだ時には、キラの言葉が救い出してくれた。
時には、今は悩むよりも動くべきだと。時には、既にもう答えを見出しているのだと。
そして時には、悩み沈み込んでも詮無い事だと。それよりも前を見るべきだと。
「ありがとう」
キラへの愛しさが溢れ、思わず携帯電話にキスをしてしまった。
マイクから通信回線越しに伝わったのだろうか。キラがうっと息を詰まらせたのがスピーカー越しに伝わって来る。そして多分、
今頃ぼんっと顔を赤くしているはず。
『…も、もう、アスランは…! そうやってメイリンさんやルナマリアさんも口説いたわけ!?』
「なっ、なんでそういう話になるんだ! 大体、俺は二人にそんな…」
『もう遅いし、切るからね、また明日ね!』
「えっ!? おいキラっ」
『帰ってくるの、待ってるから!! じゃあね!!』
ぶちっ!
一方的にまくし立てられた直後、派手な音を立てて電話は切れてしまった。
「…何なんだ、あいつはまったく…」
いくら照れたからって、あんなにいきなり切らなくてもいいのに…と思いながら、その実自分でもちょっとあれは恥ずかしかったかも、
と赤面してしまった。
電話にキスは、ちょっと…なにやらむず痒い。
…けれど、それよりももっと大きな、あたたかな気持ちが胸を満たしてゆく。
そうだ。いつまでもジメジメ考え込んでいたって、ニコルもキラの友達も還っては来ない。ならば、彼らの分まで未来へと生き抜くこと
こそ、自分たちの使命だ。
自分たちが彼らを忘れない限り、彼らの命は自分たちの心に息づいている。そう信じよう。
自分たちの心に息づく彼らに、平和で、人が人らしく活き活きと生きられる世界を、自分たちの目を通して見せてあげよう。
それでいいんだ。きっと、それで。
携帯電話を操作し、キラの画像を呼び出す。出発の見送りに来てくれた時に撮ったものだ。
「…ありがとう、キラ」
今はもう回線の切れた電話に向かって呟くと、そっと小さな画面に唇で触れる。
アスランはそのまま、暖かく穏やかな気持ちでバスルームへ向かった。