29・falling raindrops
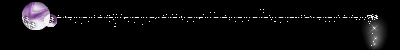
「先輩?」
はっ、と弾かれたように顔を上げると、二つ年下の少女の顔が目の前にあった。
胸元のセーラーカラーには、生徒会役員であることを示すバッヂ。
「…大丈夫ですか?」
「……………あ……」
埃の匂いがこもる閉鎖教室で、ゆっくりと頭を起こす。いつのまにか机に突っ伏して居眠りをしてしまったようだ。
不覚、としか言い様がない。
胸に飾られた小さな造花から垂らされたリボンが二つに折れてそのまま圧迫され、くっきりと折れじわになってしまっている。花は
もちろんペチャンコだ。
「…ああ。大丈夫だ。うたた寝してしまっただけだから」
「………」
彼女は、何も言わずに微笑み、隣の席に座った。
「…?」
ふと気付く、奇妙な違和感。
あまりにも暗過ぎる。それに、うるさいくらいの雨音。
携帯のサブディスプレイで確認すると、やはりまだ午後一時になろうとしているところ。自分の時間感覚が狂ったわけではなかった。
では、常でないのはこの景色のほうか。
結局居眠りしてしまったのは三十分程度だったようだが、この月面都市で三十分の間にこれほど天気が急変するのも珍しい。
「先輩、傘持ってますか?」
「…いや」
朝は晴れていた。式典の間も、教室に戻ってからも、この教室に来た時も、季節設定が夏になってるんじゃないのかと苦情を言いたい
くらい、太陽がさんさんと照りつけていたのに。
まるで嘘のように重苦しい黒雲が空を埋め尽くし、バケツをひっくり返したような土砂降り。
おかげで少しの間、もう夕方のような気になっていた。
つい先日までは、日が暮れるまで学校にいることなど珍しくも何ともなかったから。
「僕、折り畳みの傘持ってます。…あの、良かったら一緒に…」
「この勢いの雨の中で相合傘はあまり賢くないと思うぞ」
「…あ…そ、そっか。そうですよね。すみません」
微笑しながら答えると、彼女はかぁっと顔を真っ赤にして、開けかけた鞄を戻し、机の上に寝かせた。
彼女一人ならともかく、今日の自分はあまりにも荷物が多い。来るときは手ぶらだったはずなのに、卒業証書は勿論、一年のころから
様々な役員、委員会をこなし、生徒会長も務め上げ、更にあちこちの部活動に助っ人に入って大成功を収めてきたせいか、各方面から
山ほど花束を貰ってしまった。こんな雨の中で傘をさしながら持ち帰るのは…やってやれないことはないだろうが、少々憚られる。
「…ヤマトは帰らないのか? 傘はあるんだろう?」
「でも、先輩が」
「俺はもう少し様子を見るよ。荷物も多いし、…そういえば、ヤマトはどうしてここに?」
「………何となく」
ぷっ、と思わず小さく吹いてしまった。
「なんか、ヤマトらしいな」
「ザラ先輩こそ、こんなところで何してたんですか。探してましたよ、アマルフィ先輩とか、ジュール先輩とか、あとクルーゼ先生も」
「まあ、俺もなんとなく、かな」
笑われたことにムッとしたのか、少し唇を尖らせ反撃してきた彼女に、にこっと笑って更に反撃。
「先輩、ずるい」
僕の言ったことそのまんまじゃないですか、と苦笑しながら言うと、視線を窓の外に移す。
その動きにつられるように、俺も窓の外へ目をやった。
本当は、見送られるのが辛かったから。
だから、この教室から逆に見送ろうと、そう思っていた。
「………大分ましになってきましたね」
「ああ………そうだな」
確かに、雷でも鳴り出すんじゃないかというくらいの降りようだったのに、かなり落ち着いてきた。
心なしか雲も薄くなってきたような。
「……もうしばらく待っていれば、止みそうだな」
「………そうですね」
止むな。
このまま降り続けろ。
そうすれば、まだ。
「…そういえば、ザラ先輩と初めて会ったのもこの教室でしたよね」
「え? あ…ああ、…そうだったな」
少し、いや実際はもっと長かったかもしれない沈黙のあと、彼女のほうから話しかけてきた。
「ヤマトは音楽の課題をこっそり練習しようとして、俺は先生の指示で机を出してこようとして、鉢合わせ」
「…あ、やっぱり気付いてない」
「?」
「ほんとはね、ここが初めてじゃないんです。もう少し前に会ってるんですよ、僕とザラ先輩」
「え?」
目を見開いた俺のリアクションに、彼女はクスクスと笑った。
「入学式の時、桜の下で」
「お前、あれ覚えてたのか!?」
「えっ!?」
そして今度は彼女のほうが目を見開く番。
忘れるものか。
彼女を見つけた、あの瞬間を。
確かに、ただ会っただけだった。言葉を交わしたわけでもない。けれど。
桜吹雪の下で佇んでいた彼女に目を奪われて。
美しい少女。胸に小さなコサージュをつけているところを見ると、新入生だ。
ふとこちらを振り返り、優しい笑顔で会釈をしてきた。
俺は意地っ張りだから、何でもないふりを装ってポーカーフェイスの微笑を返し、そのまま通り過ぎた。胸元の名札で、学年・クラス・
氏名をチェックすることは忘れずに。
いずれどこかで何かの理由をつけて接触するつもりだった。彼女が部活に入ったなら、そこに関わっていくとか。委員会に入ったなら、
そちらに用事を作ってみるとか。生徒会長の職権を濫用しまくるつもりで。
ところが、部活や委員会が本格化する前に、ひょんなところで彼女と接点ができた。それが、この閉鎖教室での偶然の出会い。
ここは生徒数の減少によって二年前に閉鎖された教室だ。だが、閉鎖といっても使用禁止の張り紙がされているだけで、施錠はされて
いなかった。実質的には生徒会の倉庫代わりになっていて、厳密に言えば使われていないわけではなく、そういう意味では閉鎖という
言葉はあまり適当ではない。
だからキラも、こっそり音楽の課題を持ち込んで練習してやろう、という気になったんだろう。生徒会の倉庫なら、生徒会活動をして
いない時間なら人の出入りはないと。
ところがたまたま、そこへ先生からの指示を受けた俺が現れた。
お互い初めて会ったように、何故ここにいるのかを説明し、自己紹介をした。それが縁で話をするようになり、彼女を生徒会に誘ったのだ。
けれど。
そう、この時初めて会ったわけではない。
最初は、満開の桜の下。
お互いにそれを分かっていて、今までずっと言葉にできなかったのか。
「………先輩、絶対覚えてないんだと思ってた…」
「俺はヤマトのほうこそ忘れてるんだと思ってたよ。全然話題に出なかったから」
「それは先輩だって」
おかしくて、クスクス笑ってしまう。
二人して意識しすぎてたんじゃないか。
…意識、してくれていたんだろうか。
雨足が大分遠のいてきた。
目を覚ました時の土砂降りが嘘のよう。しとしとと細かい粒が落ちるだけ。黒雲はいつのまにか、白に近い灰色へとその色を変えていた。
遠くの空を見れば、雲間から陽もさしている。
「……そろそろ、帰れそうかな」
「………そう、ですね」
止むな。
もう少し。
あともう少しだけでいいから。
「………ヤマト」
「は、はい」
窓を見たまま声を掛ける。
彼女よりも俺のほうが窓寄りの席だから、彼女から俺の顔は見えない。
「生徒会のこと、頼んだぞ。お前なら来年は会長にもなれる」
「………買い被りすぎですよ」
困ったように微笑む彼女を、俺は降り返れなかった。
「でも。……僕にできる限りのことをしていきます。ザラ先輩が、託してくれたんですから」
「頼もしいな」
「頑張ります」
もう。
ほとんど、雨は降っていないのと同じくらいまで、小降りになっていた。
始まればいつか終わる。
三年前この学校に入学した俺が、今日卒業の日を迎えたように。
こうして二人でいられる時間にも、終わりが来た。
未練がましく窓の外を眺めていても、もう雨が強くなる気配はない。
「…そろそろ帰ろうか」
意を決して立ち上がり、振り返る。いつもの、先輩の顔をして。
けれど、彼女は座って俯き込んだまま、動こうとしない。
「………ヤマト?」
軽く顔を覗き込むと、彼女はますます俯いてしまう。
「ヤマト? …どうした」
「………………先、輩」
「…」
不自然に途中で詰まった言葉。
長い茶色の前髪で隠れた目元を指で拭って、肩を震わせる。
「……………」
泣いている、彼女に。
俺のほうが固まってしまって。
「……メール、しても…いいですか………時々」
「………ヤマト………」
「…返事…とか、すぐじゃ…なくて…いい…から……っ」
とうとう耐え切れなくなったように泣き出した彼女。
俺も耐えられなくなって、強引に椅子から引き摺り下ろすように立たせ、思いきり彼女を抱き締めた。
驚いてびくっと体を震わせたけれど、やがて。
俺の胸に顔を押し付け、抱きついて、声を上げて泣き始めた。
何か言いたいけれど、上手く言葉にできなくて、俺はただただ、がむしゃらに彼女を抱き締めた。強く、強く。
応えるように、彼女も掴んだ俺の制服を更に握り締める。
やがて、彼女が落ち着いてきた頃。
そっと頬に手を添えて上向かせる。
潤んだアメジストの瞳。まっすぐに、視線がぶつかる。
言葉はいらなかった。
吸い寄せられるように口づける。
唇が重なる直前、彼女がそっと瞼を閉じた。俺も目を伏せて、ただ、彼女を感じる。
長い口づけから解放して、けれどすぐに角度を変えてまた重ねた。
熱に浮かされたように軽く開いたその隙間から舌を挿し入れて、彼女の舌を掬い上げ、深く深く絡ませる。
鼻から抜ける甘い声。更に強く彼女を抱き寄せると、彼女も掴んでいた制服を離し、俺の背中へ手を回してしがみついてきた。
一体どれくらいの間、キスを交わしていただろう。
しとしとと微かな雨音だけが響く教室で、俺達はただ、抱き締めあっていた。
「………俺も、メールするよ。時々は電話もする」
「…はい」
「待ってるから。だから、ヤマトもプラントアカデミーにおいで」
えっ、と肩口に埋められていた顔が上がる。
俺は優しく微笑んで、額にキスを落とした。
「………いやです」
けれど返ってきたのは、いじけたような小さな声。
「…どうして」
「…だって…。先輩、頭いいし。運動神経いいし。かっこいいし。綺麗だし。エスコートするの上手いし」
「は?」
「周りの人達が絶対放っておかないですよ。…僕みたいな二つも年下のコドモより、大人の女の人のほうが先輩にはつりあうって思うし」
「ヤマト」
「僕なんかより魅力的な女の人、アカデミーにはきっといっぱいいるだろうし。そうしたら先輩だってきっと」
「キラ!」
厳しい声色で一喝して、間近で彼女の瞳を睨みつける。
びくっ、と震えた体は少しの間硬直していたけれど、すぐに大きな瞳から涙が溢れてきた。
「……だっ……て………!! 僕…僕なんか全然子供だし…! それに…!!」
それ以上は言わせない。
強引に、もう一度唇を重ねた。
「……信じて。俺はキラを待ってる。だからキラも、俺を追ってきてほしい」
「………先輩………」
「それとも、キラはもう進路決めてる?」
「………………オーブの…専門学校………。…情報技術のほうに、進もうと思ってたから………だから………」
もう、二度と会えないと。そう思い詰めていたのだと。
切なく揺れる瞳が、そう示していた。
「なら俺がキラを追う。俺がキラのところへ行く」
「…でも、先輩は…プラントに実家があるんじゃ…」
「別に実家があるからプラントのアカデミーを選んだわけじゃないさ。それに、卒業後の就職先として、オーブって選択肢も考えてた
からな。何年か後にする決断を今しただけの話だ」
「………先輩………」
「それより、そろそろそれ、なんとかならないのか」
「え?」
「だから。………先輩じゃなくて」
「……………えっっ」
俺が何を言っているのかようやく悟って、ぼん、と顔を真っ赤にしてしまう。
可愛い。愛しい。手放したくない。傍に居たい。
離れるのが怖いのは俺だって同じだ。こんなに魅力的な彼女を、周囲の連中が放っておくとは思えないのだから。
「呼んでみて。キラ」
「………っ」
耳や首まで真っ赤になってしまう。けれど、不意にギュウッと腕が首に回され、抱き着かれる。
「………………アス…ラン」
「…キラ」
「……アスラン」
抱き締めて。
抱き返されて。
ぬくもりを感じて。
それは無言の約束。
あなただけだと。
他の誰にも心揺らしたりしない。
あなただけを、信じて、愛するから。
いつも傍にいられなくても。
離れていても。
心は、ずっとずっと、いつもあなたと重なり合っているから。
二人の未来を照らすように、眩しい太陽の光が教室へ射し込んでくる。
――――――――――雨は、既に上がっていた。
UPの際の海原のツブヤキ…興味のある方は↓反転して下さい(大した事書いてません)
皆様、ピンクの砂ゲロがどざーっと吐き出されて大変だったのではないでしょうか。頭上にトンボが飛ばれた方も
いらっしゃるかもしれません。プッと吹いた方、爆笑された方、シラけた方、…とにかく皆様、大変申し訳ありませんでした。
つーか私もむっちゃくちゃハズいです(大爆笑) 穴があったら入っとけ海原!!! みたいな。
折角お題はいいのに…どうしたもんだろうねこの女の脳味噌は………。もうあからさまに70年代後半〜80年代前半の少女漫画って感じで。
お前時代間違えてるよと自分で自分につっこんでみたり。
そこまで恥ずかしいんだったらUPせんかったらええやんとは思うんですけど、とりあえず折角書いたので恥を晒してみました。
実際に書いたのは結構前で、お題に挑戦し始めた頃だったと思うのですが、一応卒業ネタなので時期を合わせてみました。