01・試験管で見た夢
(1)
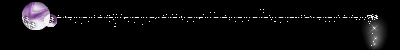
「どうぞ」
コト、と極上のキームンティーを注がれたマグカップが出される。
かしこまったティーカップではなく、彼の好みそうなシンプルなマグカップで出されることが、彼が彼女にとって「お客様」ではない
ことを示していた。
「ありがとうございます」
そう礼を告げると、いまや子供達の歌姫である元婚約者は優しく微笑み返し、自分も向かいに座ってピンク色のマグカップを傾けた。
静かだ。
少し向こうから聞こえる波の音。風にゆれる木々のそよめき。
この家がこんなに静かになることがあるのかと、アスランは感動さえ覚えて。
こんな空間を彼女と共有することは嫌いじゃない。むしろ、落ち着く。
「プラントでは、時々こうして二人でお茶をいただきましたわね」
「あ…、……ええ。そうですね」
全く同じ内容の言葉をかけようとしていたタイミングで先に話しかけられ、少し笑ってしまう。
「あなたとカガリさんが頻繁にここへ足を運んで下さって、助かりますわ」
「あいつ、キラまで無理矢理引っ張り出しますからね」
「ええ。…キラには、良い気分転換になると思いますから」
日々ここでじっと海を見つめ続けて、キラの時間は過ぎて行く。
傷ついた心を癒す時間は必要だ。けれど、見ているこちらのほうが心配になってしまう。
このまま、硬い殻の中に閉じこもってしまうのではないかと。
そうして彼が自分の世界へのめり込んで、ラクスも、アスランのことさえも、拒絶されてしまうのではないか、と。
似た危惧を、カガリも抱いているのだろう。
だからマルキオ導師が子供達と外へ遊びに出る時に、キラも一緒に連れ出して、積極的に「外」を彼に見せようとする。
そういう時には決まってラクスとアスランが留守番役を押し付けられてしまうのだが、ラクスの役割は留守番というよりも、子供達の
大半が留守になるタイミングを狙っての大掃除。アスランはその間、力仕事を引き受けたり、雨漏りの修繕をしたり。
そもそもなぜこの二人の留守番役が定番になってしまったかというと、元をたどればカガリの一言がきっかけ。大抵何人かの子供が
残ってラクスの仕事を手伝うのだが、子供と麗しい女性だけで留守番では危険だと強く主張するカガリが、キラと同行しようとした
アスランを押し留めたのだ。それがそのまま定着してしまった。
しかし、この小さな島にはこの家しかない。身を隠せるような場所もないし、ラクスを狙うならず者が潜伏しているとは考えられない
のだが。
ともかくそういった経緯で、この元婚約者同士は毎度居残り組を余儀なくされている。今日は珍しく子供達も全員遊びに出てしまった
ため、本当に二人きり。
こんなに穏やかに二人きりになるのは、婚約していた頃以来だ。
「……導師達は、今日はどこへ?」
「西側の海辺へ行くと仰っていましたわ」
「……」
西側へ向かうとなると、ここが小さな島とはいえ、結構なハイキングコースになる。
まだしばらくは、帰ってこないだろう。
アスランは時計を確認すると、思いきって尋ねた。
「ラクス」
「はい?」
「あの…、キラの…様子はどうですか」
ずっと気になっていたことを。
「様子…と言われましても。ご覧になっているとおりですわ、としかお答えできませんけれど」
「いえ、そういう意味ではないんです。その…」
歯切れの悪いアスランに、ラクスは小首を傾げる。
「……………海を、見ていますよね。テラスで。……そのまま、海に入るようなことは…」
「…アスラン?」
ラクスの表情が、すっと鋭いものへ変わる。声色にも少し険しさが混じった。
「彼が入水自殺をするようなことは、とお尋ねですか?」
いかに彼が戦争に、戦いに、命の奪い合いに、守るために奪う矛盾に、あらゆることに対して疲れきっていようと、自分の命を自ら
絶とうとするような弱さはない。
突然戦争に直面し、ナチュラル側に立つ唯一のコーディネイターという複雑な立場から世界を見て、やがて悪循環を断ち切るために起つ
決意を固めるほどに成長していても、人の命を奪い続けた自分を自ら裁くような強さは得ていない。
「…そういう意味では。わかっています。それは」
軽く首を左右に振りながら、アスランは静かに答える。
ラクスが何を言いたいのかも、自分の伝えたいことがうまく伝わっていないことも、分かっている。
原因は、自分の言葉が足りていないからだ。
「………あいつが、あの時と同じ目で…ずっと海を見ているから…」
「…?」
「海に吸い込まれてしまいそうで、怖いんです。俺は」
話は、遥か過去へと遡る。
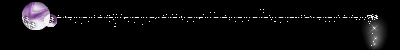
各家庭によっていろいろ生活習慣が違うんだということは、わかっているつもりだった。
初めてキラの家に泊めてもらうことになった時、母が口をすっぱくして「カリダおばさまがお母さんと違うことを言っても、それが
ヤマトさん家の決まりなんだから、僕ん家では違いますなんて言ってぐずったりしないのよ。郷に入っては郷に従えって言うでしょう?」
と繰り返したのは、きっと俺が友達の家に泊まりに行ったことがないからだろう。
それどころか、友達なんてキラ以外いないんだけど。別にそれで不自由してるわけじゃないし、無理に作ろうとも思わない。
………いや、それは置いといて。
何が一番びっくりしたって、実は、お風呂の入り方。
ザラ家では部屋を広く取るために、ユニットバスはできるだけコンパクトにまとめられていた。大人にはちょっと小さそうな浴槽に湯を
張って、その中で体を洗い、最後はシャワーで流して栓を抜く。
ところがヤマト家は洗面所とお風呂場が別になっており、しかもかなり広かった。お風呂場だけで一部屋入ってしまいそう。
大人が二人は優に入れそうな大きく深い浴槽と、これまた広い洗い場。
(要するに、ザラ家はヨーロッパスタイルで、ヤマト家は日本式だったわけだ。)
うっかり広々としたお風呂に驚いていた俺に、キラはキャッキャと喜びながらかけ湯をして、それからシャワーのスイッチを押し、俺の
髪にシャンプーを取った両手を伸ばしてきた。
「え、ええっ!?」
「ええっじゃないよ、ホラ、あっち向いてアスラン」
「そ、そうじゃなくて、お湯に入る前に洗うのか?」
「うん。当たり前じゃない、何言ってんの? ってか、え? アスランのうちって違うの?」
湯につかる前に体を洗うというしきたりもあるのだと、俺はここで初めて知った。
それについては、最初こそカルチャーショックだったけれど、そのうちこういうスタイルもいいなと思い始めたので問題はない。
閉口したのは、キラが異常に長湯なこと。これに尽きる。
「……キラ、もう上がろうよ。のぼせるよ?」
「え〜? 大丈夫だよ〜」
肩どころか頭まで湯船につかりきって、ほえ〜っと幸せそうな顔を水面に浮かべるキラ。ぽっかり口まで開けて。
「アスラン先に上がってていいから」
「もう、また!?」
他のことなら俺が先に行こうとするのをキラが引き止めるのに、こと風呂に関しては全く逆。一度本当にさっさと上がってみたのだが、
すぐに俺を追って出てくると思っていたキラは、のんびり一時間半も湯を楽しんでから出てきた。
はっきり言って、キラの長湯はちょっと異常だ。
いつだったか、一緒に食事に出掛けた母とカリダさんを迎えに行ったハルマさんのエレカが渋滞に巻き込まれて、二人の帰りが深夜に
なった日があったのだが、怒る人間が俺しかいないのをいいことに、三時間も湯につかっていたことがある。
皮膚がふやけてフニャフニャになっても居座り続けるのだからかなわない。一体何がそんなに面白いんだ。
「え? 面白いっていうんじゃなくて、気持ちいい。アスラン、お風呂嫌い?」
「嫌いじゃないけど、キラのはちょっとおかしい」
「そうかなぁ。気持ちいいのに…。僕さ、一度一日中お風呂に入っていたいんだよね」
「はぁ!?」
「ってか、お風呂に入ったまま生活ってできないかな」
「………………できるわけないだろ」
もはや怒る気力も失せて、がっくりと肩を落とすしかなかった。
幼年学校へ通い始めてしばらくして、水泳の授業が始まってから、それは更に悪化した。
キラは泳ぎが上手い。初めてプールに入ったその日に、いきなり百メートルを泳ぎきって、まだ余力があるようだった。さすがの
コーディネイターでも、この記録は特筆すべきもの。
先生は期待をかけて、すぐキラに競泳のレッスンプログラムを組んだけれど、肝心のタイムが全然伸びない。
「え〜、僕競泳より潜水がいいな〜。ずっと水の中にいられるじゃん」
…要するに、お風呂の延長なわけだ。キラにとっては。
先生が休憩のためプールから上がるよう言っても最後までグズつき、俺が腕を引っ張らないと水から出てこない。
「キラ! 一人だけ勝手な行動をするなって、この間も言っただろ!」
「だぁって…気持ちいいじゃんか。別に休憩なんて取らなくても平気なのに〜」
「平気でも気持ち良くても、先生の指示には従うの!」
「…う〜。わかった。アスランの言うことならきく」
「……………」
もう言葉もない。
数年後。
キラの長風呂は相変わらずだったが、プログラミングやデータいじりといった趣味のほうへ比重が変化し、そちらへ時間を充てるために
さっさと上がってくる日も増えてきた。
正直、俺とカリダさんは揃ってホッとしたものだ。
…その分ゲームの裏コードを見つけたり、どこかのコンピューターに侵入してみたりと、ちょっと危ないことまでし始めたのだが、
まあ俺達はまだ子供だし、ちょっとくらいのやんちゃは許されるっていう範囲のものだろう。
そう思って、安心していた矢先。
「………わかったわ。アスランもすぐ捜しに出すから。あの子なら行き先に心当たりがあるかもしれない。だから、気をしっかり持って、
カリダ」
『ええ…わかってはいるんだけど、こんなこと初めてで、私どうしたらいいか』
自室からリビングへ降りてくると、母がカリダさんと電話をしていた。どうやらカリダさんは公衆端末からのようだが、遠目のモニター
越しにも顔色の悪さがわかる。
『あっ、そ、それに、こんな時間からアスランくんを出歩かせたら、それこそ危ないんじゃ…』
「何言ってるの。うちのアスランはそんなにヤワじゃないわ。なんたって私の息子なんだから。それに、キラくんを見つけ出すセンサー
みたいなもの、持ってるような気がするし」
『…レノア…』
「とにかく、あなたは一度家に戻って、あとはアスランに任せて。アスランでも見つけ出せないようなら、警察に連絡しましょう」
『ええ…わかったわ。ごめんなさい』
「何を謝ることがあるの。困ったときはお互い様。私のほうが借りは多いのよ? こんなときくらい協力させて頂戴」
『レノア………』
涙ぐむカリダさんの声を聞きながら俺は部屋に戻り、出掛ける仕度を整えた。
再びリビングに戻ると、母が電話を切ったところだった。
「アスラン」
「キラがどっか行ったって言うんだろ? 行くよ、捜しに」
「ん。それでこそ私の息子」
よしよしというよりも、わしわしっという具合で、母にしては珍しくダイナミックに頭を撫でられた。
「キラくん、いつのまにか部屋から消えていたそうよ。窓が空いていたから、こっそり出たみたい。カリダがそれに気付いたのが、十五分
程前ですって」
「十五分前?」
腕時計を確認する。
そろそろ十一時になろうとしていた。十時すぎまではネット対戦をしていたんだから、まだ飛び出してそう時間は経っていないはず。
「まったく、あいつ…」
「アスラン、十五分ごとにこちらから定期連絡を入れるわ。その度に経過を教えて。それから、タイムリミットは十二時。それまでに
見つけ出せないようなら」
「聞こえてたよ。わかってる。それじゃ、行ってきます」
「頼んだわよ。気をつけてね」
母に見送られて、俺は家を出た。