11・金網の向こう側
(1)
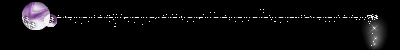
「お手柄だよアスラン」
「は?」
突然隊長に呼ばれたかと思うと、そんな言葉をかけられた。
何が手柄だというのだろう。足付きには何度も逃走を許し、ストライクも落とせずにいるのに。
………ストライク。
思い描いた白い機体。あの中にはキラがいる。大事な大事な幼馴染、いや、それ以上に想う少女。それなのに、なんの因果か彼女は敵と
なり、地球連合軍の新造戦艦に乗って、同じコーディネイターである自分達ザフトを相手に孤軍奮闘しているのだ。
彼女がラクスを引き渡す為に一人足付きから飛び出してきた時も、来いという言葉を拒絶された。その際、これを好機と見て潜んでいた
クルーゼ隊長による奇襲はラクスの凛とした姿勢によって防がれ、力づくでキラをこちらへ連れてくることさえ叶わなかった。
「ストライクに乗っているのは君の友人だと言っていたな。確か、名を『キラ』と」
「は、はい」
つい感傷に浸りそうになってしまったアスランの意識を、クルーゼの声が断ち切る。
確かに、クルーゼの前でキラの名前を出した覚えはある。けれど、それが何だというのだろう。
「キラ。…キラ・ヤマト。月面都市コペルニクスにて、君と共に幼年学校に通う。性別、女性。年齢、十六歳。家族構成、父・ハルマ・
ヤマト、母・カリダ・ヤマト。兄弟なし。五月十八日生まれ、血液型A。…違うかな」
「………い…え……」
違いはしない、違いはしないが、だが何故彼女のことをそこまで。
そんなアスランの疑問を見透かしたように、くすとクルーゼの口元が小さく笑った。
「君が呟いたその名が引っかかってね。調べてみたのだよ。そうしたら『当たり』だ」
「…当たり、とは…? 隊長、何を仰りたいのか私には計りかねます」
何故だか増大していく不安。
「お手柄だ、と言っただろう。…いや、君にとっては嬉しくない手柄かもしれんな…」
続くクルーゼの言葉は、その不安を肯定するものだった―――――――。
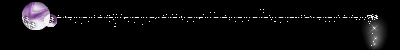
ドサリ、と転がる地球軍の青いパイロットスーツ。
「フン…こいつがストライクの…」
まだ包帯の取れないイザークが、敵意と憎悪の篭った左目でぎらりとそれを睨みつける。
ディアッカも興味津々という様子で、そしてニコルも真剣な表情で成り行きを見守っている。いや、顔面蒼白になっているアスランを
気遣っているのかもしれない。
ストライク捕獲作戦中もイージスの動きは鈍く、ストライクを逃がそうとしているようにさえ見えた。急遽ミラージュコロイドの技術を
そっくりそのまま流用し、隠した艦を八隻もこの作戦に投入してきたのだ。足付きにも、捕獲対象となったストライクにも、逃げ場など
ありはしない。またイージス一機だけで退路を作れるわけもないというのに。
医療チームの衛生兵が、ぴくりとも動かない彼女からヘルメットを取る。
「!」
ついに露にされたストライクのパイロット。
血の気が完全に引いた顔色に、アスランは声を上げそうになってしまう。
「ウッソ、まだガキじゃん」
「?」
医療チームのチーフが、ディアッカの独り言を聞きつけて振り返った。
「君達はこの捕獲作戦の主旨を聞かされていないのかね?」
「は? …捕獲作戦の主旨、って。何だか知らないけど、殺さずに浚って来い、ってことだろ」
「………」
「ま、あんだけの高圧電流に晒されて生きてるってだけで、ナチュラル離れしてるとは思うけどさァ。コーディネイターでもヤバいって
電圧だったんだろ? 実は死んでんじゃない?」
「こいつが…こんな奴が…!?」
呆れたように続けるディアッカと、わなわなと震えるイザーク。その目前で黙々とパイロットスーツが取り去られてゆく。
「…それにしても…まさか、女性が乗っていたなんて…」
「………」
当惑するニコルの横から、ぎり、とイザークが奥歯を噛み締める音がかすかに響いた。
その間にも作業は続き、キラは地球軍の制服のインナー姿に。そしててきぱきと作業が始まる。
「心拍、僅かに正常値を下回っていますが、許容範囲内です」
「血圧、想定値範囲内」
「脳波、異常なし。体温も少し低いですが平常範囲内、異常は認められません」
「…ほとんど何ともないってことかよ」
うそだろ、と呟くディアッカと、ほっと息をつくアスラン。
「さすがはスーパーコーディネイターだな。こりゃ、かなりすごいぞ」
ぽつりと呟いた一人の衛生兵に、怪訝そうなクルーゼ隊の視線が集まる。
「…おい。貴様今何て言った!?」
「え…っ、ちょっ、何だいきなり!」
ぐいとイザークに胸倉を掴み上げられ、うろたえる衛生兵。
「コーディネイターだと!? ふざけるな!! こいつは地球軍の…っ」
「ただのコーディネイターではない。スーパーコーディネイターだ。イザーク」
シュン、と背後の扉が開き、クルーゼが入室してきた。はっとして衛生兵から手を離し、敬礼を返すイザーク。ニコル達も続いて敬礼を
返したが、アスランだけはやはり心配そうに、ちらりと後ろの様子をうかがっていた。
「あちこちに早急な手回しが必要な作戦だったのでね。君達への説明が事後になってしまってすまなかった」
「隊長、どういう事ですか、今仰った…」
「スーパーコーディネイター、かね」
「…」
ともすれば子供向けのヒーロー番組か、という響きになってしまうその単語も、クルーゼが発するとどこか意味深に聞えるのが逆に
恐ろしい。
「つまり彼女は『そういう』存在だということだ」
「………仰っている意味がわかりません!! あれはストライクの!! 地球軍の」
「それには色々と不幸な事故が重なっていたのだ。例えば…彼女が幼い頃ブルーコスモスに襲われ、研究者でもある両親はその際惨殺された
こと。そして、彼女だけが辛うじて保護されたこと。保護した夫婦が、ナチュラルであったこと」
「!? それでは、キラの実のご両親は………」
「アスラン?」
一人訳知り顔で語気を荒げたアスランに、ニコルが不思議そうに振り返る。
「…そうだ。既に他界している」
「………そんな」
「おい…ちょっと待てよ。お前、ストライクのパイロットのこと今…、………知ってんのかよ、あいつの事」
「………彼女は……… !?」
悲痛な面持ちでキラを振り返ったアスランは、そこで信じられない光景を目にした。
なんと衛生兵達はキラを治療する様子もなく、わけのわからない電極やコード類をキラの肌に次々繋げていたのだ。
それは先端が心電図を取るときのようなパッド状になっているものもあり、また針のように刺すものもあり、洗濯バサミのようなもので
指を挟んでいるものもある。
それらは全て、何かの計測器に繋がっていた。
「ちょっと待て!! 何をしている!! 治療が先だろう!!」
「被験者は治療の必要な状態ではありません。クルーゼ隊長、すぐに拘禁室へ移しますので、そのように上へ連絡をお願いします」
「うむ」
「被験者!? 拘禁室!? 隊長、これはどういうことですか!!」
「すまんなアスラン。こればかりは私の力ではどうにもならん」
さしてすまないと思っていなさそうな、感情のこもらない言葉がクルーゼの口から発せられる。
「キラをどうするつもりですか!! あんな、わけのわからないものを体中につないで…あれじゃまるで実験動物だ!!」
「…隊長、まさか……」
さすがにディアッカも冷や汗を流した。
いかに自分達と戦ってきた地球軍の先鋒とはいえ、コーディネイターだというのならまがりなりにも同胞だ。なのに。
なのに、まさか。
「彼女は研究施設へ送られることになっている。彼女は唯一すべてが『設計』どおりに産み落とされた、この世で唯一最強の『スーパー
コーディネイター』なのだ。研究者達が黙って放置するわけがあるまい」
ぐらり、とアスランの意識が重く揺らぐ。
何てことを。
一体、何てことを。
「…………っ!!!」
「そ…んな………」
イザークとニコルも、その意味するところを察して、ぞくりと背筋に寒気が走った。
確かに散々辛酸を舐めさせられた敵だ。仲間も討たれた。それはわかっている。だが、年の近い少女がそんな扱いを受けるということを
断言されていい気味だと思えるほど、彼らの思考回路は凝り固まってはいなかった。
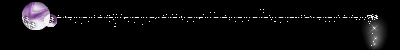
――――ピッ。
――――ピッ。
計器が反応するたびに、機械音が小さく響く。
中央には、医療用の白いガウンを着せられたキラが、ぐったりと横たわっている。薬でも打たれているのだろう。目はうっすらと開いて
いるが、時折機械的にぼんやりまばたきをするだけで、何かを見ている様子はない。
いっそ服など着せても無意味と思わせるほど、キラを取り巻くコードは数を増していた。ガウンの合わせの隙間から、袖から、裾から、
様々な色や太さのコードが出ており、部屋中に積まれた機器類へ繋がっている。
薄く開いた唇。その下唇にまで、クリップ状の電極らしきコードが繋げられていた。
「くそ………!!!」
ガシャン、と鉄条網を鳴らす。
「アスラン、血が…!」
ニコルの声も届いていない。ぎりっ、とそれを握り締めると、傷付いた指からつぅっと血が流れ、制服の袖を汚した。
檻の中には、電磁波だか電波だかをシャットするらしい、透明だが分厚いカーテン。更に檻の外側には、最新の艦の中にあるには
不似合いな鉄条網。
まるで大昔の童話に出てくる荊の森のように、完全に檻を覆っている。
出入り口だけではなく、視界までも塞ごうとするかのよう。
ほんの数歩で、届くのに。
こちらへ来いと何度も呼びかけた。
けれど、まさかこんな形で彼女を迎えることになるなんて。
「くそぉぉっ……!!! キラ…!!」
こんな目に遭わせたくて呼び続けてきたのではない。
「うわっ、………なんだよこれ!」
背後から不意にディアッカの声がする。驚きと嫌悪が入り混じったような声が。
「ディアッカ、イザーク……」
ニコルが振り返って、しかしすぐ視線を落としてしまう。
ぎりっ、と奥歯を噛み締める音が微かに響いた。
「…っ……!! …くそッ!!」
がしゃん! とイザークも拳を鉄条網に打ち付ける。
「おい! お前、手…!」
「オレはこんなものが見たかったわけじゃないッ!!!」
「…イザーク…」
気遣わしげなニコルの声も、やはり本人の意識には留まっていない。
彼女は、この世で唯一のスーパーコーディネイター。
遺伝子コーディネイト研究の最先端をゆく第一人者、ユーレン・ヒビキ博士。妻であるヴィア・ヒビキ博士と共に、ブルーコスモスの
テロの標的となった。夫妻の遺体が発見された後、まだ赤ん坊であった双子は発見されぬまま捜査は打ち切られたが、現場の状況から
殺害されたものと思われる―――――。
その双子の片割れこそが、キラ。
キラ・ヒビキ。
ユーレン・ヒビキ博士の実子であると同時に、彼が唯一遺した、たった一人のスーパーコーディネイター。