11・金網の向こう側
(2)
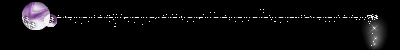
「…そういや、カガリって子はどうなったんだろうな。自分の出生知ってるんなら、心配してそうなもんだけど」
「………その子は…ナチュラルだったんでしょう? …あまり…考えたくはありませんが…」
まさかそれがオーブ五大名家のトップであるアスハ家の皇女、カガリ・ユラ・アスハのことであるとは思いもつかないニコルは、
そこまで言うと口を噤んだ。
「けど、彼女が生きてたんなら…」
「………キラは…一人っ子だ」
ぼそり、とアスランが言葉を紡ぐ。暗く、低い声で。
「…少なくとも、ヤマト家に保護されたわけじゃないってことか」
「そんなことはどうでもいい!!! おい貴様!! こんなものをこのまま黙って見ているつもりじゃないだろうな!!」
ぐいっとイザークがアスランの襟を掴んで乱暴に引き寄せる。
「貴様はあいつの幼馴染なんだろう!! こんなことを許しておくつもりか!? このまま実験動物にされるのを指をくわえて見ている
つもりか!!」
「冗談じゃない!!!」
カッとして叫び返し、イザークの襟元を掴み返すアスラン。
「キラを実験動物になど、させてたまるか!!!」
「けど実際、どーすんだよ。この状況じゃ連れ出すどころか、中に入るのだってかなり厳し」
「シッ!!」
ディアッカの言葉を遮ったニコルが、じっとキラに見入る。
何だ、と振り返ったアスランとイザークも、あるかすかな音に気づいて、ディアッカとともにキラへ視線を移した。
「……………あ………す………………………あ…す………………ら」
ひゅーっ、という喉が掠れるような音の隙間から、キラの声が、ほんの少しだけ。
「キ………っ」
叫びそうになって、咄嗟に息を飲む。大声をあげては、必死で振り絞っているキラの声が聞き取れなくなってしまう。
「…ご………………ご……め…………ん…ね…………」
鉄条網の針金が、それを掴んだアスランの手に食い込む。
「………アー…………ク……………み…………な……」
弱弱しく動く唇には、挟まれているクリップを振り払って外すような力など、残っていない。
「……………ま………も……………な………………く……て…………」
ぎりっ、と噛み締められたイザークの奥歯が軋む。
「………ご…………め………………………な……さ…い……………」
虚ろな瞳が、こちらを向く。焦点が合わないまま、ただじっとアスランのほうへ向けられる。
「……………ア…………………ス………ラン………」
たどたどしい言葉。思うように舌や唇が動かないのだろう。
「めい…わ……………ば………っか…り………………か…け……………ご……め…………………ね………」
「もういい!!! …もういい、キラ………!!」
「…キラ、さん……」
アスランが声を絞り出したのと、痛々しげにニコルが呟いたのがほぼ同時。
「くそっ、…ええい!! こんな気分の悪い話があるか!!」
「だよねぇ。………ここはさ。やっぱ、オレらが何とかするとこじゃないの」
いつもは飄々としているディアッカも、さすがに真顔だ。
「…ニコル。ディアッカ、イザーク」
緩み切ってしまいそうになる涙腺をぴんと引き戻して、アスランは三人を振り返る。
「キラを助けたい。…頼む。手を貸してくれ」
今まで一度だって見たこともないような厳しい表情で。
「……最初からそう言え! フン、これで一つ貸しだぞアスラン」
「となると、きちんと計画を立てないといけませんね」
「そうそう、やるなら徹底的にやろうぜ」
ニッとガッツポーズをして見せて、それからキラに向き直るディアッカ。
「待ってろよ。すぐそっから助けてやるからな。お姫様」
「…うわ…。ディアッカ、キザっていうか何ていうか…」
「話が決まったら行くぞ。ここじゃモニターカットもままならん」
監視カメラの存在を懸念して、サッと部屋を出て行くイザーク。ディアッカも続いて出て行って、更に続いて退室しようとしたニコルが
降り返る。
「行きましょう、アスラン」
「ああ。…ありがとう」
「忘れないで下さい、僕にも一つ貸しですよ」
にっこりと微笑むニコルに、笑い返すアスラン。…うまく、笑えただろうか。
「……キラ……ごめん。すぐに出してやるから」
再び伏せられてしまった虚ろな瞳。規則的に響く機械音。ひゅーっ、ひゅーっ、と掠れるような呼吸。
キラ。
こんな目に遭わせる為に呼び続けてきたんじゃない。
必ず、助ける。
アカデミー時代から衝突が絶えなかったイザ―クとディアッカだが、呼吸さえ合えば心強い味方だ。四人で力を合わせれば、必ずキラを
助けることができる。必ず、助け出して見せる。
決意を胸に、アスランはニコルと共に退室して行った。キラを救い出す計画を練り上げるために。
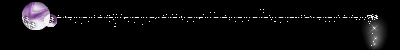
『かつて一世代目のコーディネイターを迫害したナチュラル達と、行っていることがまるで同じではありませんか』
プラントの歌姫。老若男女みんなのアイドル。ピンクの妖精。
そんなイメージを完全に吹き飛ばしたラクスは、毅然とした指導者の顔で、パイプの太いマスコミ機関を通じ、ザフト上層部が発案し
強行した『ストライク捕獲作戦』の裏に隠された真実を世間に公表し、告発した。
『確かにこの少女は、コーディネイターでありながら、地球軍に組していた。そのことを司法の場で裁くというのならともかく、ただ
彼女が「珍しい種だから」という理由で、このような拷問まがいの仕打ち。これはザフトの掲げる正義に反する行いではありませんか』
今頃研究者達は、苦々しい表情でこれを見ていることだろう。
そしてザフトの上層部は、青い顔で慌てて事態収拾へのシナリオを書き始めているに違いない。
『そもそも彼女は、ザフトによるヘリオポリス崩壊に巻き込まれた友を救うために、咄嗟にその場にあったMSを駆り、そのまま友人を
守るためだけに戦ってきただけのひと。彼女を戦いに巻き込んだことさえ、ザフトの側に責任の一端があるのです。ヘリオポリス攻撃の
理由について、ザフトはヘリオポリスで極秘に地球軍の最新機動兵器が開発されていたからだと発表しています。しかし、それがこんな
形で何も知らない市民を巻き込んで良い理由と言えますか? この事件さえなければ、彼女は地球軍と関わることもなく、また自身さえ
知らなかった出生の秘密を暴かれることもなく、このような拷問を受けることもなかったのです』
「………すごい迫力ですね」
私服姿のニコルが、呆然とラクスの演説に聞き入っている。
優しい歌を穏やかに唄い上げる愛くるしい少女が、権力を持つ大人達を相手に堂々と啖呵を切るとは、想像もしていなかった。
「…怒らせると母上よりも怖い人かもしれないな」
「この映像ってさ、電波ジャックでプラント中に流れてんだろ? えげつねぇな…」
「ジャックじゃないですよ。番組枠をきちんと取って、スポンサーもちゃんと得ている正当な放送です」
「………ますますえげつねぇっての…」
すっかり私服で寛ぐ三人は、寛いでいるはずなのに、なぜか背筋が凍るような感覚。
「それで、あいつはまだキラ・ヒビキの部屋か」
「ええ。目が覚めた時、傍にいてあげたいんだそうです」
「しっかしなぁ…あっさり婚約まで解消しちまうなんて、いいのかよ?」
「やるなら徹底的にって言ったのはディアッカじゃないですか」
「いや、そりゃそうだけど…」
「途中から首謀者がラクス嬢にすり変わっていたような気がするぞ、オレは」
「追求しないほうがいいですよ、イザーク」
ラクスの訴えをBGMにしつつ、三人はこれ以上掘り下げて考えないことに決めた。
ここは、クライン家の屋敷。
キラ救出の計画をラクスに打ち明け、彼女にキラの身柄を預かって欲しいと頭を下げたのはアスラン。ザラ家でキラを匿えれば一番
良いのだが、家長である父パトリックは国防委員長。ザフトのトップにいる人物だ。認めたくはなかったが、『スーパーコーディネイター
研究』について、パトリックが影で糸をひいている事は客観的に考えて明白なこと。そしてジュール家の家長であるエザリアは急進派
であり、タッド・エルスマンも同じく急進派。二人とパトリックとは同志と言える。アマルフィの家は比較的穏健派ではあるが、ザラ家と
対抗できるほどの力はない。
現在ザラ家と対等に張り合える力があり、キラの救助に力を貸してくれそうな人物は、クライン家の一人娘、ラクス・クラインの他に
思い当たらなかった。
幸い、アークエンジェルでキラと友情を育んだらしいラクスは、キラの現状を知るや、アスランに代わって救出計画を率先して練り
始めたのである。しかも、当初の彼の考えよりも更に過激で、徹底した計画を。
娘から事の次第を聞いた現プラント最高評議会議長シーゲル・クラインは、旧友パトリックが極秘裏にスーパーコーディネイターの
研究を進め、いずれはMSと連動した生体兵器を『開発』しようとしていることを看破し、娘の計画を全面的にバックアップ。今や議会は
完全にザラ派とクライン派に分裂しているが、ザラ派のほうが分が悪いのは子供の目にも明らかだった。
監視システムを麻痺させてキラを救い出したアスラン達は、それぞれの愛機と共に全速でヴェサリウスから脱出。その足でクライン邸へ
入り、今はキラの目覚めを待ちながら事態を静観している。
勿論、プラントを守りたいという思いが薄れたわけではない。だが、『ザフト』が道を外していると知った今、盲目的に軍上層部の
命令に従い続けることはできない。
鳥篭のような外観のサンルーム。
同じ透明な壁の向こうでも、あの拘禁室とは雲泥の違いだ。草花や小鳥に囲まれて眠るキラは、とてもとても穏やかに眠っている。
水差しの白湯を新しくしてきたアスランは、そっとベッドサイドの椅子に座り、キラの手を取った。
脳細胞の活動を抑え、神経伝達物質の活動を抑制し、意識を朦朧とさせる薬を、キラは通常の五倍もの濃度で投与されていた。あのまま
放置していたら廃人と化していただろう。
研究者達が検体としてキラを扱うには、その方が都合が良いというわけだ。
そんなことになる前に助け出せて良かったと、アスランは心底ラクスに感謝して止まない。
「キラ」
薬の後遺症で眠り続けるキラ。だが医師の話によれば、薬が抜ければ自然と回復し、目覚めるとのこと。
「キラ。…ラクスも、ニコル達も、お前に会いたがってる」
一つ貸し、なんて言っていたイザーク達だが、いつの間にかキラ本人に興味津々だ。誰か本気で惚れやしないだろうかと、こっちは内心
ヒヤヒヤしているというのに。
幼年学校の頃から苦労して虫をつけないようにしてきたのに、ここに来て三人も恋敵が増えるのは面倒だ。しかも相手が厄介すぎる。
「俺も、お前と話がしたい」
戦っていた時のわだかまりが嘘のよう。今は素直に、離れていた間のことを話し合いたいと思う。
「足付き…いや、アークエンジェルって言うんだったな。彼らはちゃんと捕虜として、軍規に則って身柄を保護してある。…友達にも、
会えるから」
今の状況では難しいが、クライン派がザフトを掌握した後なら、きちんと申請すれば面会要請は通るはずだ。
「……………だから」
目覚めて。
また、微笑んでほしい。
さあっ、と爽やかな風が、レースカーテンを揺らしてサンルームを通り過ぎてゆく。
キラの髪を撫で、頬を撫でて。
…顔色もすっかり良くなった。
今にも寝惚け眼をこすって起き上がり、時計を見るなり遅刻だと言って慌てて準備を始めそうな気がする。
大昔の童話。
荊の森の奥で眠っていたお姫様は、どうやって目を醒ました?
もうクリップの痕も残っていないピンク色の唇に、そっと唇を重ねる。
「…………………ん……」
まるで童話が現実になったかのように。
「……? …アスラン………?」
鉄条網の奥で意識を奪われていた、アスランにとって唯一の姫君が。
「…おはよう」
「……………おはよう。キラ」
目を醒まして。
可憐な白い花のように、優しく微笑んだ。