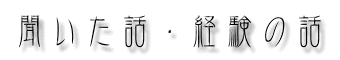
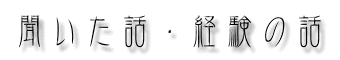
ここで述べてることはあくまで本を読んだり・聞いたり・自分なりの経験をもとに書いています。
参考程度に見てやって下さい。
m(宜しくお願いします。;)m
 国内で流通している各産地
国内で流通している各産地
|
 Dead
or
Alive
Dead
or
Alive
|
| ・ アンタエウス |
| 東京 海外との気温差(比較) | 1990年代 | |||||||||||
| 標高 "約30〜50m" | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 最高気温 | 10℃ | 10℃ | 13℃ | 18℃ | 23℃ | 25℃ | 29℃ | 31℃ | 27℃ | 21℃ | 17℃ | 12℃ |
| 最低気温 | 1℃ | 1℃ | 4℃ | 10℃ | 15℃ | 18℃ | 22℃ | 24℃ | 20℃ | 14℃ | 8℃ | 3℃ |
| India(Darjeeling) | |||||||||||||
| 標高 "約2134m" | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 9℃ | 10℃ | 15℃ | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 15℃ | 10℃ | |
| 最低気温 | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 10℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ | |
| Nepal(Kathmandu) | |||||||||||||
| 標高 "約1337m" | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 17℃ | 19℃ | 24℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 22℃ | 18℃ | |
| 最低気温 | 2℃ | 4℃ | 7℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 18℃ | 13℃ | 8℃ | 3℃ | |
| Malaysia(Cameron) | |||||||||||||
| 標高 "約1500m" | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高気温 | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | |
| 最低気温 | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | |
|
※生活環境温度: 上記の温度を見ても分かるように通常であれば飼育環境は26℃あたりが限界と思われる。 が、ブリード物などであれば30℃位の環境下でも耐えることができます。 しかし、耐久テストなど虫に負担がかかるような事は出来る限りやめませう。 |
 アンタエウスとは、オオクワガタの中の一種で「Dorcus Antaeus 産地名」(DA産地名)と呼ぶことが主です。
アンタエウスとは、オオクワガタの中の一種で「Dorcus Antaeus 産地名」(DA産地名)と呼ぶことが主です。| ・ 幼虫の管理 |
 一昔前まで、自然界と同じように材飼育もしくは、
一昔前まで、自然界と同じように材飼育もしくは、| ・ 成虫の管理 |
 プラケースにホームセンター等で売っている昆虫マットを3〜4cmひき、
プラケースにホームセンター等で売っている昆虫マットを3〜4cmひき、| ・ ♂♀の組合せ |
 ペアリングですが、♂♀の成熟は配慮が必要なようです。
ペアリングですが、♂♀の成熟は配慮が必要なようです。| ・ 産卵 |
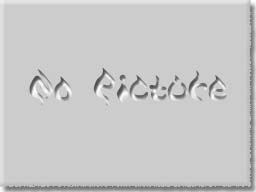 セット用ケース: 縦50cm×横50cm×高さ50cm位の大きさが目安です。
セット用ケース: 縦50cm×横50cm×高さ50cm位の大きさが目安です。| ・ 幼虫の採り出し |
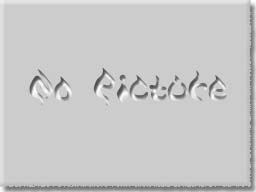 ペアリングもうまくいき産卵ボックスにセットしたら約1.5〜2ヶ月位して中を確認します(割り出し)。
ペアリングもうまくいき産卵ボックスにセットしたら約1.5〜2ヶ月位して中を確認します(割り出し)。