lullaby
(1)
単独行動
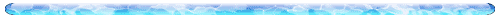
lullaby
(1)
単独行動
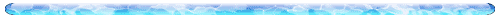
「ハァ? 遊びに行ってこい? オレ一人でぇ?」
「一人が嫌なら、ステラでも連れていけよ」
冷静に言い返すスティングはモニターに向かったままで、ムカつくことにこちらを見ようともしない。
「お前はどーすんだよ」
「情報収集」
「そんでオレだけバカやってこいって?」
「あのな。遊びに行けって言ったのは喩えだバカ。実際このへんをどのくらいザフトの連中が掌握してるのか、街を見て来いってことだよ」
「フーン」
(なんだよ、だったら最初っから偵察って言っとけよな)
文句を心の中だけで愚痴って、両手を頭の後ろで繋ぐアウル。
しかし、自分達『エクステンデッド』と呼ばれる強化人間に、こんな休暇じみた時間が訪れることがそう多くないことも、彼は理解
している。その貴重な休暇を堪能しても、問題ありとスタッフの奴らが判断したら、あっさり楽しんだ記憶を消されてしまうことさえも。
何を忘れて何を覚えているかなんて、よくはわからないけど。でもあいつらが自分のアタマの中も操作してることは知ってる。
それで強くなれるなら、今の力を維持できるなら、構わない。どうせあの研究所に放り込まれた瞬間から、運命は決まっている。
だったら、その運命に勝ってやる。生き残って、生き延びて、最後に笑うのはオレだ。
(まァオレの場合、母さんが研究者だったってのが救いっちゃ救いかな)
物心がついてから両親と引き離されたり、戦争で身よりがなくなって送り込まれてきた『ご同類』達は、いつも死神に魅入られたような
目をしていた。
血に怯え、戦闘マシンになることを拒み、耐えられなくなって発狂し、ジ・エンド。或いは、人を殺すという行為を恐れ戸惑っている
うちに、逆に相手にやられてお終い。
大抵の連中がそんな末路を辿る中、スティングとステラ、そしてアウルだけは違った。
(オレが違ったのは…やっぱ、母さんが褒めてくれたから、だよな)
いい子ねアウル、あなたの成績がいいと私も鼻が高いわ。…美しい笑顔と共に、優しい母の声が甦る。
人殺しの能力を身につけていくことに怯える、周囲の仲間達。しかしアウルは、それこそが母と会う唯一の方法。
最高得点を出せば母さんに会える。一番多く敵を殺せば母さんに褒めてもらえる。母さんも、褒められる。
(…我ながらガキくせぇ)
けれどアウルにとって、唯一母親こそが大切な存在。スティングやステラも気の合う仲間で大切には思っているが、母親はまた、別格だ。
―――――そう刷り込まれていることを、本人は知らない。それは『母さん』という単語をブロックワードに設定するための、入念な
インプリティング。
「このへんの地理は覚えてあるな」
ぼけーっと立っているアウルに、言外にさくさく行ってこい、と告げるスティング。アウルは溜息をついて、なんとはなしに見入って
いたモニターから視線を外した。
「ハイハイ、行きゃいーんだろ、行きゃ」
「ステラが妙なとこにフラフラ行かないように、注意してろよ」
「わぁかってるって」
開け放たれたルーフバルコニーから、爽やかな風が通り抜ける。アウルはその風に逆らいながら外へ出た。
偵察用にネオが借りてきたこの貸し別荘を、三人は結構気に入っていた。日当たりが良くて採光もいいし、風は気持ちいいし、ベッドの
寝心地はいいし、海は目の前だし。本当にちょっとしたバカンスと勘違いしてしまいそうだ。
だが、屋根裏部屋の天窓から屋根の上に出て見渡すと、海岸線を辿った先にザフトの基地が見える。勿論全体を見渡せるわけではないが、
三人の視力を持ってすれば、出入りする船や軍船、軍人達の姿を裸眼でチェックすることもできる。
それを見つけた瞬間、息抜きのつもりでちょっとくらいのんびりして来てもいいぞ、なんて冗談混じりのネオのセリフに、まったく
真実味がなくなった。
いや、一人真に受けている困ったちゃんがいる。
「ステラー? おーい、ステラー」
その可愛い困ったちゃんの名を呼びながら、アウルはルーフバルコニーの隅にある短い階段を降りる。降りてしまえば、波打ち際は
すぐそこだ。津波でも来たらどーすんだよ、なんて物騒なことを考えながらステラの姿を探し続けていると、彼女はなんと、波打ち際で
踊っていた。
アーモリーワン潜入の時にネオから「プレゼント」された独特なシルエットのドレス。ステラはそれが大層お気に入りのようで、
飽きもせずくるくると回転して、スカートや袖をひらひらと宙に舞わせ続ける。
「………まだやってんのかよ、バカ」
この間のが街で浮かれたバカの演出なら、今度はバカンスで浮かれたバカの演出だろうか。
だが、つまさきを波打ち際で遊ばせ、腕をすらりと伸ばして舞うステラは、まさに夢中といった様子。こんな時に邪魔すると、途端に
しょんぼりとヘコまれてしまうのだ。
ステラにとって、風と踊り続けることのほうが楽しいか。それとも、ディオキアの街へ遊びに行くと言えば、そちらのほうに興味を示す
だろうか。
「……………」
想像してみる。ディオキアの街で自分に手を引かれて歩くステラの顔は、しょぼんと地面に向けられ、歩みはとぼとぼと遅い。
決定。
(一人で行こっと)
アウルはそのまま、街の中心部に向かって歩き出した。
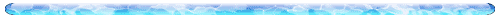
活気、…というのだろうか。こういうのを。
「♪ほーっし〜のぉ〜っ、ふるばしょでぇ〜っ♪」
「違う違う、ここは手こっちだって」
「ええ〜っ、こうだったって!」
「あぁん、地球にもラクスちゃんのPV配信してくれないかなぁ〜! フェンス越しに一回見たっきりじゃ覚えらんないよ〜」
「さあさあ安いよ、お肉が安いよ! なんたってザフトさんからの入荷だからね、新鮮で安全で、上物の肉が沢山入ってるよ!! ああ、
そこの水色の髪のボーヤ、ハムでもどうだい、食べ盛り!」
「おや、ザフトの! はいはい、タバコだね」
「腰の具合どうですか、おじいさん」
「いやいや、この間あんたがさすってくれたのが効いとるよ、ありがとうね。ホレ、一箱オマケ」
「ありがとう。それじゃお返しだ。これ、湿布ね」
「おやおや、まあまあ、すまないねぇ。わしゃこれからアンタたちのおる基地に足を向けては寝られんのう。ハッハッハ!」
………浮かれている、のほうが的確な気がしてくるアウルだった。
(うーわ。ふっつーに軍服で街歩いてるよコイツら)
流石にザフトレッドの姿は見かけないが、一般兵である緑の軍服はそこかしこで見かけることができるほど、すっかり街に解け込んだ
様子。道で遊んでいる女の子達の持つスピーカーからは、ラクス・クラインとかいうプラントのアイドルの最新曲が流れ、振り付けを
真似しようと必死だ。
こんにちは、何か困っていることはないですか、…なんて、どこかのボランティアと間違えてるんじゃないかと突っ込んでやりたい
ようなことを、すれ違う街の住民達に尋ねながら歩くザフト兵。
(気っ色悪い光景)
これはステラを連れてこなくて正解だったかもしれない。こんな状態で、彼女がするりとどこかへ紛れてしまったら、それこそザフト兵
と関わるハメになりかねない。
仮にも彼女も綿密な調整を受けた最高峰のエクステンデッドだ。うっかり自分がファントムペインの一員だなんてことを口にしたりは
しないだろうが、不必要にザフトと接触することは好ましくない。
ならステラをしっかり掴まえておけばいいのだろうが、どうにも掴み所の無いあの天然娘は、ふとした瞬間、シャボン玉のように
さりげなく目の届かないところへ行ってしまうことがある。
あれは訓練の賜物などではなく、天賦の才に違いない。
――――――などと考えながら歩いていたのがいけなかったのか、不意に店から出てきた人影と、肩が当たってしまった。
「おっと」
「うわっ!!」
軽く触れただけだったのだが、相手はダンボールを三箱も抱えていて、バランスを崩して焦ったらしい。一番上の箱を落とすまいと
あたふたしている間に、カシャンという軽い音が響いた。続いてアウルの踏み出した一歩の下から、ぐしゃ、というあっけない破壊音。
「あっ、悪ィ!!」
咄嗟に足を上げるが、時既に遅し。そこには原型を留めていない眼鏡のなれの果てが。
「あっちゃ〜…」
「ああ、いいよいいよ、それより靴に破片刺さってない? 大丈夫?」
「へ? ぶっっ」
顔を上げると、そこにはダンボール箱。思わずウケてしまった。
「え? …あ、そっか」
相手からどう見えているのか察したのか、壊してしまった眼鏡の持ち主もクスクス笑い始めた。
「マジごめん。ちょっとボケッとしてた。こういうのってすぐベンショーできるもん?」
「え? いいよそんな。僕の不注意だし」
「いや、でもさ」
アウルは訓練や薬物投与で操作されて、とんでもない視力を持ち合わせているが、眼鏡というのは普通、視力を補強するためのもの。
中には眼鏡やコンタクトを外すと何も見えないという人もいるはず。ないと困るのでは。
まあ、こいつ一人困ったところで自分には関係ないといえばないのだが、さすがに今回のは後味が悪い。普段なら絶対にこんなヘマは
しないのに。どうやら街に当然のようにのさばっているザフトの連中のことを、自分で思っている以上に不快に感じていたようだ。
「…ちょっと待って」
ダンボールを抱えたままでは話しにくいと判断したのか、単に重くて辛くなってきたのか、ぶつかった相手は店の脇に停めてあった
ワゴン車の後部扉を開き、ダンボールをすべて手際良く車の中へ納めてしまった。
ふぅ、と息をつきながら扉を閉め、こちらへ向き直る。
(…うわっ、可っ愛いー……)
思わず目を見張ってしまった。
つばを後ろにして被った白いキャップの隙間から、襟足を長めに残した茶色の髪がこぼれ、陽の光に照らされて部分的にキラキラ光る
のが綺麗だ。帽子を使って前髪を上げ、おでこを出しているのだろう。長袖と半袖のTシャツを重ね着して、胸元には何か文字が刻まれた
ドッグタグ。どうやらだぼっとしたストリート風を目指したようだが、逆に彼女の華奢さをやたらと強調する結果になっており、成功して
いるとは言えない。キュロットスカートかよとつっこみたくなる半ズボンからすらりと伸びる足は、そのまままだ履き込まれていない
真っ白なスニーカーへと続く。この足もまたやたらと細い。
ついじーっと見ていると、相手はかあっと顔を赤くしてしまった。
「えと……僕のかっこ、変…?」
「え!? いや、ヘンってこたないけどさ…って、それよりメガネ!」
「あ、それはほんとにいいんです。ぶつかった僕が悪いから。前、見てなかったし。それより、靴…」
「へーきへーき。こっちはほんとマジへーき」
いまどき骨董品みたいな黒ぶち眼鏡だったらしく、ぽっきりと折れた黒いつるの破片やら、割れたレンズやらが多少刺さってはいたが、
自分の足まで傷付けてはいない。ちょいちょいと突付けばポロポロと取れる程度だ。
「だからさ、踏んだのこっちなんだから、ベンショーするって」
基本的に自分達エクステンデッドはただ働き―――つまり、先行投資に莫大な資金が投じられているので、兵役労働という形で軍に
その前払いの資金を返還している形になるのだという。そのため、給料はない。基本的には。
その代わりと言えるのかどうか、父親みたいにネオがお小遣いをくれる。どうやらこの金の出所は彼個人の財布の中らしく、冗談抜きで
「お小遣い」なのだ。新型奪取成功の際には、そのご褒美と称して臨時収入をくれた。
だが、そんなに金の掛かる趣味があるわけでもない。服は軍やネオが支給してくれるし、たまに暇つぶしのネタを買うくらいしかない。
そんなわけで、塵も積もれば山となるとばかりに、実は三人とも結構お金持ちだったりする。このくらいの臨時支出は、痛くも痒くもない。
しかし彼女はうーんと考え込んで、それから、にこっと笑いかけてきた。
「それじゃ、弁償のかわりに、お茶とケーキおごってくれる?」
「へ?」
「で、僕が君の分をおごるから。それでお互い様、ってことじゃだめ?」
「……………」
それって弁償のかわりになんないじゃん、と言い返してやることもできたのだが、あんまりにも彼女が可愛いので、ついぽかんと口を
あけたまま止まってしまった。
「三つ先の通りに、美味しそうなお店があったんだ。僕の車でいいよね?」
「へ?」
彼女はそれを了承と受け取ったのか、さっきダンボールを積み込んだワゴン車へ歩み寄っていく。
「あー……………。………オッケ、わかった」
こんな可愛い子と知り合える機会なんて、次があるかどうかもわからない。
後で記憶が消されるかもしれないけど、そんなことは関係ない。だってオレは今を生きてるんだから。今楽しまなくて、いつ楽しむ?
悪戯っ子みたいに笑って、アウルは彼女の車の助手席に乗り込んだ。
そして。
彼女ではなく『彼』だったということは、車内の雑談ですぐに判明するのだった。