lullaby
(5)
天使
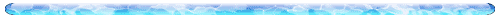
lullaby
(5)
天使
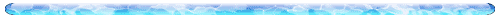
無言のまま走り続けるワゴン。やがて、小さな小さな展望公園の脇に止まった。
周囲に人気はない。その展望公園は、街と街を繋ぐ幹線道路の脇に、駐車場の代わりのようにちょこんと存在している。人気を期待する
ほうが無理というものだろう。…それを見越したカップルくらいは立ち寄るかもしれないが。
エンジンを止めてキーを抜き、車を降りるキラ。アウルも無言で彼に続いた。
展望公園と銘打たれているだけあって、景色は最高。斜面に落ちないよう設置されている柵の傍にまで歩み寄る二人。
ここからは、ディオキアの街の半分近くと、美しい海を一望できる。
夕暮れで赤く染まる空。穏やかに打ち寄せる波。
遠くかすかに響く波の音が、二人の心を落ち着かせてくれる。
「…なんで知ってんの。オレのこと」
アウルのほうから、そう口火を切った。できるだけキツくないように、責める口調にならないように気をつけながら。…こんなふうに
気を遣うのは、キラに嫌われたくないから。
声をかけながらそっとキラを振り返る。彼は一瞬だけ古い傷が痛み出したのを堪えるような瞳になったけれど、すぐに穏やかな表情を
取り戻し、ただじっと海の彼方を見ていた。
「……………前に………、戦ったことが、あるから」
えっ、と声にならない声がこぼれる。
「二年前………」
「…ああ」
自分達から一つ二つバージョンの古いタイプの「お仲間」が、二年前の戦争の時に実戦投入されていたことは、データだけでだが知って
いる。なんとかグリフェプなんとか、とかいう薬を投与して強化するタイプの連中で、自分達のいたロドニアからも一人、出ていたはずだ。
…セクションが違ったから、そいつと顔を合わせたことはないが。
初めて実戦投入された『エクステンデッド』。確か初陣は、オーブ解放戦だったはず。その後もヤキン戦で三人とも散ってしまうまで、
戦い続けていたはずだ。その彼らと戦ったことがあり、そしてコーディネイターであるということは、恐らく。
「…キラって、ザフト?」
「ううん」
「けど、トモダチはザフトにいるんだろ? それに、エクステンデッドと戦ったって」
「エクステンデッド?」
「オレらのこと。…知らないの?」
「そこまで詳しくはね。僕が分かってるのは、とにかく地球連合軍の中にコーディネイター並に強化されたナチュラルの人がいる、って
ことだけだから」
「え、ウソだろ? ザフトだったらもうちょっと情報…」
キラがザフトだと決めてかかる自分の言葉に、自分でちくりと痛みを感じてしまい、不自然に声が途切れてしまう。隣で困ったように
小さく微笑んだキラは、思いも寄らないことを口にした。
「アウル、本当に僕はザフトじゃない。むしろ、以前は地球軍にいたんだよ。ほんとに、ちょっとの間だけだけど」
「え!?」
「野戦民兵、っていうの? 最初はなりゆきでね。…でも、やめた」
「………でも…そんじゃ、戦ったって…」
「クライン派、って言われてるところに、いたから。…いるから、かな」
「…アークエンジェル?」
「………うん」
ああ。
すとん、と何かがアウルの中に降りて来た。
曲がった事を嫌う、真っ直ぐで純粋な心。軍人として訓練されたコーディネイター二人を相手に一瞬で勝利をおさめることのできる力。
そして、あの時自分が感じた、尋常ではないレベルの危険信号。
――――多分キラって、あいつだ。…六枚羽根の天使。
フリーダム。
データでしか見たことのない機体の名が、すんなりと脳裏に浮かんだ。
すべての争う者共を鮮やかに斬る不殺不敗の天使。戦う力だけを奪う、無茶苦茶な天使。
その戦いぶりを映像で見させられた時の衝撃は忘れない。こんな戦い方のできるヤツがこの世に存在するのかと、モニターに目が
クギ付けになった。
このパイロットがその気になれば、全てのMSのコクピットを一閃することも可能だろう。だがそれをせず、戦う力だけを残酷にもぎ
取って行く。取り残された兵士の屈辱も恐怖も知ったことではないとばかりに、生き残ることを強要する。
こんなに自分勝手に戦えるヤツ、きっと他にいない。
彼が本当にフリーダムのパイロットかどうかはともかく、少なくともアークエンジェルだと断言する彼にとって、地球軍に属し戦う
自分は敵なのだろうか?
ちょん、とキラの服をつまんでみる。
彼はこの世で一番綺麗な瞳をこちらに向けて微笑むと、『何? どうしたの?』と言葉にする代わりに小さく首を傾げて見せた。
ほっと肩を落とし、なんでもないと顔を横に振って、キラにくっつくようにして隣に並ぶ。
良かった。キラにとって『オレ』は敵じゃない。
そのことに安心したり、自分から彼に対して敵意などひとかけらたりとも湧かないのが少し不思議だったけれど、その理由はすぐに
はっきりした。
だって、キラが大好きだから。
キラも一緒に戻って、そのまま四人でいられたらいい、なんて夢見ている自分がいるから。
スティングと、ステラと、そしてキラと―――――。
もし、誰も知らない、誰も追ってこれない場所で、四人で暮らせたら、それはどんなに暖かく幸せな日々だろうかと、当て所ない夢を
見てしまう。…ああ、ステラがゴネたら大変だから、ネオも呼ばなきゃ。
らしくない、かもしれない。
だけど、もしそんな夢みたいなことが現実になったら、どんなに倖せだろう。
肩と腕を触れ合わせたまま、二人はただ空と海を見つめる。
やがて空から夕暮れの色が消え、夜の色が広がってゆく。
「……………遅くなっちゃったね。…送るよ」
すっとキラの体温が離れた。
離したくない、と衝動的に掴む。
「アウル?」
真っ直ぐなアメジストの輝き。
世界一美しい宝石。たった一対しかないきれいなもの。
この眼を、絶対に忘れない。
「………いや。……んじゃ、送ってくれる?」
そっとキラの腕を離すと、逆にその手を握られた。
「行こう」
車に戻るまでの、ほんの十数歩の距離を、オレ達は手を繋いで歩いた。