lullaby
(6)
また会う日まで、
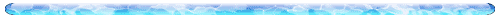
lullaby
(6)
また会う日まで、
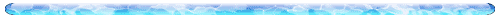
貸し別荘の前に着くまで、二人は無言だった。
ザリザリとタイヤが石を噛む音を立て、駐車スペースにワゴンを止めるキラ。
エンジンの音も止まって、車内は完全に騒音のない静かな空間になった。
「…あ〜あ、着いちまった」
「もうちょっとゆっくり遊びたかったね。…でも、僕もそろそろ…時間だし」
「…だよな。うん」
シートにもたれていた背を起こし、ちらりとキラを見る。
彼は名残惜しそうに、優しくこちらを見つめていた。
「また会おうね、アウル。戦場じゃない、どこかで」
「………」
即答できなかった。
きっと、戦場で出会う確立のほうが、高い。
…いや、クライン派は今影を潜めているというから、今のところは心配ないだろうか。しかしこれからザフトとの戦いが激しさを増せば、
彼らは二年前のように戦争を止めるべく現れるかもしれない。
(………らしくね)
YESと頷く代わりに、アウルは肩をすくめた。
(だったらさっさとザフト潰しゃいーだけじゃん?)
オレにはその力もある。
キラと戦場で出会うような事になる前に、ザフトを負かせて戦争を終わらせる。
以前は、戦争が終わった後の自分の姿なんて、思い描くことはなかった。どうせまた研究所に戻って、更に強化するための訓練や実験に
明け暮れる日々なんだろうと漠然と思っていた。
けれど、今は違う。
戦争が終わったら連合と手を切ろう。ひょっとしたら拿捕されるかもしれないが、そうなったら研究所を破壊してでも出て行ってやる。
ステラはネオの側から離れないかもしれないが、スティングはノッてくるだろう。あいつも退屈が大嫌いなヤツだから。
そうして、自由の身になって、キラを探すんだ。
キラと一緒に、ずっとずっと笑い合って生きるんだ。
言葉で答えない自分に、少し不安そうな顔をするキラ。安心させるように、自信満々でニッと笑って見せる。
「戦場じゃないとこっつか、世界中どっこも戦場じゃなけりゃいーんだろ? オレがサクッと終わらせてやるよ、こんなの」
一瞬きょとんと目を見開いて、ぷっと小さく吹き出すキラ。
「すっごい自信」
「あっ、なんだよ笑うなよ、めちゃくちゃマジなんだからさ〜」
「うん、ごめん。…そうだね。早く終わるといいね。こんな争いは」
「ああ。まかしとけって」
「うん」
綺麗な綺麗な笑顔。
目に焼き付けて、シートベルトを外した。
「………それじゃ、またな」
「うん。またね」
さよならは言わない。
きっとまた会おう。また、どこかで。
(絶対に忘れないから)
何度調整を受けても、絶対にキラのことだけは忘れない。
絶対に。
ジメジメするのは性に合わない。ひょいと車から降りたアウルは、三歩ほど車から離れて、笑ってキラに手を振る。
キラも微笑んで手を振り返して、それからサイドブレーキを外し、エンジンをかけた。
別荘からではなく、その横からスティングが現れた。キラは彼に目を留め、小さく会釈する。スティングも無難に微笑んで会釈を返し、
隣に歩み寄って来た。
ザリザリと石を噛むタイヤの音。道路まで車を戻したキラは、最後にもう一度アウルに手を振って、そのまま走り去って行った。
キラの姿が見えなくなるまで、車が見えなくなってしまうまで、アウルは手を振りつづけた。
「………おい。ナンパして来いなんて言った覚えはねえぞ」
苦々しいスティングの言葉に、思わずぷっと吹いてしまった。
「やっぱ女に見えるよなぁ」
「はぁ? あれ、男? …まあいい」
無害と判断したのだろう。スティングはすぐに真剣な顔に変わる。
「それよりお前、街でステラを見なかったか?」
「ステラ? 見なかったけど?」
チッと舌打ちをするスティングに、まさか、とイヤな予感。
「どこにもいないんだよ」
「はぁ〜!? なにしてんだよあのおバカは!」
「知るか。とにかく探すぞ。お前も手伝え。迷子になってザフトに保護されたりしたら面倒だ」
「わかってる」
「多分海沿いに動いたんだとは思うがな…少し遠出するぞ」
「っとに手が焼ける!」
ブツブツ言いながら、二人は海岸沿いに走り出した。
そうしてアウルは、近い未来に自分を倒す相手と、そして―――キラが言っていた『ザフトにいる友達』と、そうと知らずに出会うこと
になる。
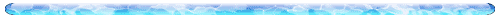
エクステンデッド達の短い休日は終わった。
放任されていた子供達は、次なる戦いに備えて揺り篭に入れられる。
いつもならただの昼寝程度にしか思わない「調整」。だが今日は、その寝台へ上がるのに踏ん切りが必要だった。
(大丈夫。大丈夫………オレは絶対忘れない)
そう言い聞かせて、アウルはひどく寝心地の良い寝台に寝転んだ。
透明な天井が降りて来て、寝台はカプセルになる。
いつものように、すぐに心地良い睡魔が訪れ、逆らわずに瞼を閉じた。
瞼の裏に少女のような少年の顔を思い浮かべたのは一瞬。その後は、ゆらゆらと波に揺られるような気持ちいい感覚だけが、アウルの
眠りを支配していった。