SHADE AND DARKNESS
nine
「水の証」
(5)
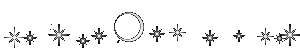
…そう思い直し、納得したはずだったのに。
「ええーっ!? お、おんなじペットロボばっかり、色違いで、ですか!?」
「やぁだメイリン、今更なに驚いてんのよ。結構有名な話じゃない。ねぇキラ?」
「うん。私も聞いたことあるよ、どこだったかな…何かのインタビューの時だったと思うんだけど」
「ウッソー! なんであたしだけ知らないの〜!?」
「そんなのあたしに聞かれたって知るわけないでしょ」
「あはは。でも、この子以外のハロ達とも会ってみたいかも…アスラン様がラクス様に贈られたハロ達、きっとみんな可愛いんだろうなぁ」
「まあ。きっと今頃ネイビーちゃん達、おうちでくしゃみをしていますわね」
「えっ、ハロってくしゃみするんですか!? かわいい〜!」
「しゃっくりをすることもありますのよ」
「ええー!? ハロのしゃっくりー!? 聞いてみたぁーい!」
すっかり打ち解けた少女達の弾む話し声。その後ろで、マネージャーが腕時計をちらりと目にする。さっきからその頻度が上がっている
のは、アスランの気のせいではないだろう。なにしろラクスは、なんだかんだと理由をつけ、もう一時間も予定の時間をオーバーさせて
このお茶会を続けていた。
確かに、キラだけでなくホーク姉妹とも和気藹々と話している。決してキラだけを特別扱いして延ばしているわけではない。それはわかる。
だが、これ以上は不自然だ。コンサートのリハーサルにも差し障る。
今自分が果たすべき役目は、ラクスの夫として彼女をたしなめ、楽しい時間に終わりを告げることだろう。
でも。
でも、と、何度も諦めたはずの想いが、とっくに割り切ったはずのことが、どうしても頭をもたげてくる。
このままキラを、連れ去ってしまえたなら。
自分の元へ、連れ戻すことができたなら。
どこの誰とも知らない婚約者などに、みすみすキラを渡すことなどできるものか。
アスランと呼んでくれなくてもいい。ただ傍にいてくれれば、それだけで。
だめだ、とどこかで声がする。けれど、ずっとずっと押し殺して来たキラへの想いが、押し殺したからこそ増幅してきた想いが、堰を
切って溢れ出す。
「―――――――っ」
コンコン。
はっ、と顔を上げるアスラン。立ち上がって、そしてキラを…と思い詰めたその瞬間を見計らったかのように、楽屋のドアがノックされた。
結局、立ち上がったのはアスランではなくマネージャー。足早にドアに駆け寄り、その向こう側にいる人物と声を交わすと、アスランの
ほうへ歩み寄って来た。
「ご主人様にお客様です」
「え?」
告げられた名前は、そう意外なものではなかった。だが、今このタイミングで自分を尋ねて来る理由はないと思うのだが。
「別のお部屋をご用意致しましょうか」
ここはラクスの楽屋で、一般市民である少女達もいる。ましてや尋ねて来た客人はラクスではなく、アスランを尋ねてきたのだ。確かに、
アスランが退席して別室で対応することが適当と思われる。
「…、いえ、ラクスさえ構わなければ、この部屋に」
「こちらに、ですか?」
マネージャーの視線がラクスに向けられる。彼女はにっこりと微笑み、頷いた。
「わたくしは構いませんわ」
答えてから、あ、と三人の少女を振り返るが、キラ達は少し緊張した面持ちで揃って頷いた。
政府の要人であるアスランにわざわざ尋ねて来る人物がいるのなら、一般市民である自分たちがイヤだとごねられる立場ではないと、
どうもそういう様子らしい。
「で、ではこちらにお通ししてもよろしいですか?」
「ええ」
差し支えのある人物ではない。それに、第三者が入ってくることで、落ち着くことができたなら。…今自分は、間違いなくキラを連れ
去ってどこかへ逃げようとしていた。何もかもを放棄して、またいつかのように彼女の思いも幸せも全てを無視して。
おそらくラクスは、そのあたりのことまで見越して構わないと答えたのだろう。
「失礼します」
落ち着いた声。続いてドアが開き、長身の男性が現れた。紳士的な立ち居振舞いは、見る者に安心感を与える。
歩み寄って来る男を、アスランは立ち上がって迎えた。常に微笑みをたたえる男の顔が優しい微笑へと変化し、更に柔らかな印象になる。
「ご無沙汰しております、ザラ国防委員長。ヘブンズパレス完成のお祝いにと、ご挨拶に伺う機会を探してはいたのですが、いや、結局
遅れ遅れになってしまって申し訳ありません」
「いえ、博士。ヘブンズパレス完成については、こちらのほうからお礼に伺うのが筋です。こちらこそわざわざ足を運んで頂いて恐れ入ります。
博士のご協力がなければ、市民達にこれほど喜ばれる街にはならなかったでしょう」
「そう言って頂けると、プライベートの時間を削って尽力してきた甲斐があります」
優雅に差し出された右手に、こちらも手を重ねる。社交辞令とわかってはいるが、それだけではないと思わせる優しい雰囲気を、彼は
常に身に纏っていた。
そういえば、とアスランに倣って立ち上がっていたラクスを振り返る。
「家内とは、初対面でしたね」
「ええ。完成祝賀パーティーに出席させて頂いていれば、直接お会いする機会があったのかもしれませんが…ああ、勿論『プラントの歌姫』
としての奥様のことは、よく存じ上げておりますがね」
「ラクス、こちらはヘブンズパレスのスペシャルアドバイザーとして、カラーデザインや街区構想プラン等に加わって頂いた、ギルバート・
デュランダル博士。心理学、臨床心理学を専門にされているが、遺伝子学の分野にも明るい方で、心療内科や精神科の医師でもある」
「初めまして。ラクス・ザラ・クラインですわ。この度は主人が大変お世話になりました」
「ギルバート・デュランダルです。こちらこそ、お力になれて光栄です」
ラクスとも握手を交わす。
ちらりとキラの様子を伺うと、彼女は座ったままぽかんとしていた。
おや、とホーク姉妹に視線をやると、二人も呆気にとられている。
「お取り込み中に突然の訪問で、驚かれたのではありませんか?」
穏やかな声にはっと意識を戻す。そうだ、言われてみれば確かに、なぜわざわざラクスの楽屋に? 挨拶だけなら折を見てアスランの
執務室を尋ねればいいだけの話だ。自分の目でヘブンズパレスを見たかったのかもしれないが、それにしてもラクスのコンサートに合わせて
くる必要性はない。それとも多忙な彼のこと、今この時しか機会を作れなかったのだろうか。
それを声に出して尋ねる前に、彼はにこりと微笑んだ。自分にではなく、ラクスでもなく、何故そちらへと疑問を抱かせる方向へ顔を向けて。
「……………な………」
声はアスランが発したものではない。
かといって博士でも、ラクスでもない。
ガタンという音を立てて立ち上がり、顔を真っ赤にさせたキラが叫んだ。
「なんで先生がここにいるのよ!?」
えっ、とアスランの顔が強張る。
…そうだ、デュランダルは心療内科と精神科の医師でもあると、さっき自分で紹介したところではないか。
ではまさか、デュランダルはキラの主治医なのか。
セドリックの元から離れた後のことは全く知らされていない。ラクス宛に送られて来たあの写真だけだ。主治医がどういう人物か、
それも当然アスランもラクスも知らなかった。それがまさかこんな形で知ることになろうとは、なんという偶然だろう。
そのデュランダルが、困ったように小さく首を傾げた。
「…『先生』?」
「あ…」
「いくら久しぶりとはいえ、それはないと思うがね。キラ。それとも、長い間君との時間を作れなかった私への罰のつもりかい?」
「なっ、なによそれ! すっごい嫌味!」
「それを言うなら、君が私を先生と呼ぶのも嫌味だよ」
「仕方ないでしょ! 癖みたいなもんなんだから!」
「癖というものは、直そうと思い努力しなければ直らないものだよ。とすると、君には直す気がないということになる。ふむ、困ったな」
「どういうヘリクツよ! もうっ、知らない!! 勝手に困ってれば!」
ふんっ、と勢いよくそっぽを向くキラ。
ホーク姉妹はげんなりしている。
「ま〜た始まった…」
「先生、わかっててわざとやってるでしょ。からかうのが楽しくて仕方ないって顔してます」
「フフ、メイリン君は鋭いね。今からでも心理学を専攻してみてはどうだい?」
「まあ、皆さん博士とお知り合いですの?」
微笑みを浮かべたまま、さりげなくラクスが会話に入り込む。彼女もどういう事か知りたいのだろう。
「ええ。実は」
にこりと微笑んだ博士が、明日の天気を告げるようにさらりと答えた。
「彼女…キラ・ヤマトは、私の婚約者なんです」
UPの際の海原のツブヤキ…興味のある方は↓反転して下さい(大した事書いてません)
と、いうわけで。
キラの婚約者の正体はギルバート・デュランダル氏でした。
本編においてアスランをあっさり手駒にした経歴のあるこの方なら、手も足も出まい(笑)
そして密かにギルキラ一度書いてみたかったんです。えへ。
一度本編に添った形で何か書けないかなぁ…短編でもいいから…ってだめだギル相手じゃ短くまとめられる自信がない…。
って。気付けば今回のお話から全く話がそれている。すみません。