NieR crossing Abyss
ナツ ノ ユキ
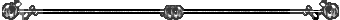
<2025 夏 新宿>
雪が降る。
廃墟と化した街に、静かに雪が降る。
風が吹けば舞い上がる、溶けない雪。それは塩の粉。それは死の灰。遺灰同然の塩の粒。
白雲が多い尽くした空は、重く暗い。
人気のない廃墟。半ば朽ちた建物の中に、息を潜め隠れている兄妹がいた。この世界には黒くて恐ろしいモノが跋扈している。彼らに
見つからぬよう、二人はひたすらに息を潜めて生きていた。
二人に両親はない。だから助けを求められる相手などいない。国の偉い大人がいる場所は分かっているが、あいつらは既に自分達を
裏切った。絶対に信用できない。
病弱な妹を守るため、兄は一人恐ろしいモノと戦い、食料を探す。日々はその繰り返し。
彼の傍らには黒い本があった。装丁も中身も総て黒い、『黒の書』と呼ばれる物である。表紙には人の顔が立体的にデザインされており、
色と相まって見る者に不気味な印象を抱かせた。
本には意志があり、それはいつも甘い毒を舌に乗せて囁きかける。昨日も、今日もまた同じコトバを。
「力をやろう…」
防寒のフードを目深に被った兄は、寒さと空腹に耐えて膝を抱え座り込んでいる。いつ恐ろしいモノが襲ってきても妹を守り戦える
ように、常に鉄パイプを握り締めて。
「妹を守る力が欲しいだろう。食べ物に困らぬ力が欲しいだろう。私はそれを授けることができる。お前の『 』と引き換えに」
「……………」
びきっ、と亀裂が走ったような音を立てて眉間に険しい皺を刻んだ兄はやおら立ち上がり、一縷の容赦もない全力でもって『黒の書』
を蹴り飛ばした。
ここがワールドカップのピッチであれば間違いなく相手ゴールに突き刺さりネットを破って大歓声を受けたであろう見事な蹴りだが、
残念ながらここは廃墟であり、キックを受けたのはボールではなく本。朽ちた什器やらコンクリートの壁やらにバコンバコンぶつかった
本は、へちゃりと床に落ちた。装丁に傷一つないのは見事であるが、本文のほうは折れ曲がったまま床に押し付けられた恰好になる。
本は悲鳴こそ上げなかったものの、激痛に耐える苦悶の呻きまでは押し殺せなかった。
「………ア、アッシュ! ここは滑らせるように蹴るシーンだぞ、いや、蹴るというよりも、遠くへやるといったほうが正しい!」
「うるせえ!! てめえにそういうことを言われると本気で頭にくるんだよ、ヴァン!! 何もかも全部奪っておいて力をやるだと!?
ふざけるな!!」
「ま、待て、これはクロスオーバーなのだ、原作の話を持ち出すものではない! それに、言い草に文句があるのなら私ではなく本編の
『黒の書』のほうに」
「ほう? 踏まれてえらしいな」
「や、やめんかっっ!! ここにいるのは腹を空かせ衰弱した兄妹だぞ、そのように殺気立っていてはおかしいだろう!」
「こんな鉄パイプ一本でマモノを次々倒していくような奴が、衰弱してるわけねえだろうが!!」
「それだけ必死だということだ!! ええい、埒が明かぬ。ナタリア王女、次のセリフを!」
「あら。マモノとバトルチュートリアルは飛ばしてよろしいのかしら…、…っ! ゲホッ、ゲホッ!」
「ナタリア!?」
演技ではなく咳き込んだ様子の声に、アッシュは顔色を変えて駆け出した。そして駆け出す第一歩で思い切り『黒の書』を踏み付けた。
ぐをっと呻く『黒の書』など意にも介さず、アッシュはついさっきその『黒の書』が蹴飛ばされぶつかった什器をぐるりと回り込む。
荷物や廃材、他の什器でバリケードのように守られたその場所には、お揃いの防寒着に身を包んだ少女が座り込んでいる。
「ナタリア、大丈夫か」
「え、ええ…ごめんなさい」
「顔色が悪い。芝居は中断して、医者に」
「いいえ、大丈夫ですわ。顔色は…その、体が弱いという設定でしたから、お芝居にリアリティが出るようにと思って、少し障気を吸い
ましたの。そのせいだと思いますわ」
「な…っ」
「大丈夫ですわ、これが終わったらローレライが浄化して下さるというお約束ですから」
「そ、そうか…」
ほっと肩を下ろすアッシュ。そういうことなら、と一つ咳払いをして、芝居に戻った。
「少し待っていろ。今食料を探してくる」
「ごめんなさい、お兄様…」
「おに…」
役柄とはいえむず痒い呼ばれ方に、何ともいえない顔になってしまうアッシュ。後からあの顔は見ものだったとルークやガイにからかわれ
癇癪の元となるのだが、それはまた別の話。
「わたくしの体が弱いばかりに、お兄様にばかり苦労をさせてしまって…」
「そんなことを気にするな」
普段のアッシュからは考えられないほど柔らかな微笑み。思わず頬を染めてしまうナタリアの頭を、防寒着のフード越しに優しく撫で、
そして再び立ち上がる。鉄パイプを握り締めて。
歩き出そうとして、ふと足を止めた。嫌悪の眼で睨むのは、ナタリアの傍らにある『黒の書』。先程アッシュが蹴り飛ばし踏み付けた
のとは別の、同じ本。
「…いいか。何があってもその本にだけは触るなよ。絶対にだ」
「え、ええ…。わかりましたわ」
分かり易くフラグを立て…もとい、妹に注意を残して、アッシュは今度こそ歩き出した。
まるでナタリアを守るように囲い込んである什器と崩れた廃材。ぐるりと見渡す風景は廃墟の一言。ここは元々大型スーパーだったが、
いまや見る影もない。健在であった頃は所狭しと豊富な食料品が並んでいた筈の什器は見事に空、兄妹は廃材の間に落ちているものを
探りながら命を繋いでいる。だが、その僅かに見つけたなけなしの食料は既に底をついており、ペットボトルの水が多少残っている程度だ。
もっとも、それだけの水でも兄妹にとっては恵みなのだが。
そろそろ外へ行かなければならないだろう、と兄は覚悟を決める。もう、妹から目を離さずにいられる圏内には何も無い。一旦外へ出て、
別の入り口か外壁に空いた穴から入る等して探さなくては。スーパーなのだから裏に回れば倉庫もあるはずだ。先に略奪されていなければ
良いのだが。
(だが、その間ナタリアにもしもの事があったら―――…)
懸念を現実にするかのように、うぞ、と影が揺らめいた。それはどこからともなく起き上がる。見た目には実態があるのかないのか
判然としないような連中なのに、黒くて金色の影を揺らし、鉄パイプで殴りかかれば血飛沫を飛ばすそれ。断末魔は悲鳴ではなく、子供が
ぶつぶつと呪文を唱えるような囁き。気味悪いことこの上ない。
アッシュは、この『黒くて恐ろしいモノ』の正体を知っていた。
だからこそ、何としてでも妹に近付けるわけにはいかなかった。
例えソレが『 』であったとしても、戦わなければならない。倒さなくてはならない。
「雑魚が…近寄るんじゃねえ!!」
流石のアルバート流で次々とマモノを倒していくアッシュ。マモノはわらわらと起き上がってくるが、生産(というのもおかしいが)
速度が殲滅速度に追いつかない。ビュッと鉄パイプの血を振り払い、不敵に笑う。
「フン、この程度なら楽勝だな」
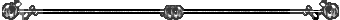
「おや、聞き捨てなりませんねぇ」
「とはいえ現状ではこれ以上の強さのマモノは出せない。どう対処する、ネクロマンサー」
「それはまあ、強さを調整できないなら数で調整するしかないでしょう。これ以上展開を狂わされると修正が利かなくなりますから」
「了解した。………ところで、ひとつ尋ねたい」
「はい、何でしょう?」
「何故私が貴様の下で動かねばならないのだ」
「システムの調整は公平に、ということではありませんか? ルーク達のほうからは私が、グランツ謡将のほうからは副官であるあなたが。
悪くない人選だと思いますが」
「………」
「ほらほら、操作をお願いしますよ。先に進まないとティアの出番も来ませんが、それでもよろしいので?」
「…くっ…ティア…」
かたや妹命、かたや教え子命。
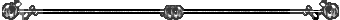
「っ、チッ!!」
鉄パイプを振るう手が血で滑る。だが唯一の武器であるこれを手離すわけにはいかないと、ぬめる手を防寒着の裾で拭った。
「くそ、どうなってやがる!!」
多くても二、三体しか現れなかったマモノが、ぞろぞろと七、八体近く現れるようになった。ゲーム画面なら半分くらいは敵で埋め尽く
されている状態になる。オタオタでも二匹と十匹では訳が違うのと同じで、大変よろしくない状況だ。
こうなったら譜術でまとめて、と術の構えに入りかけるアッシュだが、舌打ちして鉄パイプを構えなおす。そうだ、この世界に音素
(フォニム)はないのだ。あるのは魔力。だがそれを行使するには、…行使するには。
攻撃してくるマモノの拳をガードし、さっき踏まれてページが曲がったままになっている『黒の書』を一瞥する。鉄パイプを振るっては、
また『黒の書』を睨む。
『妹を守る力が欲しいだろう』
徐々に兄を蝕む毒。甘い、甘い毒。
それがどんなに危険な毒か分かっている。決して手を伸ばすものかと決意した。
だが。
妹を守る―――――――その誓いのほうが、重い。
「………くそおっ!!」
まるで剣のように鉄パイプを一閃、マモノを薙ぎ払う。そして、ずんずんと『黒の書』に歩み寄った。
「フ、アッシュよ、ようやくふごっっっ」
背表紙からガッと踏み付けられ、曲がったページが更にぎゅうぎゅうに開く。
「とっとと力を寄越せ」
「………………………………………」
しくしくと泣きながら、『黒の書』は白い閃光を発した。
びく、とマモノ達が震える。
強烈な光。光。光。光。光光光。光光光光光光光光光。
やがて収束する。マモノ達は警戒を緩めず、光の爆心地を見つめる。そこから現れたのは、兄。だがさっきまではなかった禍々しい
魔力が立ち上っている。その傍らには、兄の肩より少し高い位置で付き従うようにふわりと浮く『黒の書』。必死で折れたページを元に
戻そうとしている様子は間抜けでしかないが、それが禍々しい魔力を立ち上らせているので更に間抜けである。本なのだからページを
真っ直ぐに伸ばして閉じれば自然と直るだろうに、律儀にも『ニーア』のシーンを再現したいらしい。
再現もなにも元に戻そうとしている動作が間抜けでまったく台無しなのだが。
ひしめくマモノ達はアッシュに気圧され、それでもまたぞわりと動き出す。アッシュはまったく動じることなく不敵な笑みを浮かべ、
譜術の要領で意識を集中させた。
ヴォン、と真っ黒な手が現れる。手といっても巨大な、アッシュの背丈の倍はありそうな魔力の手だ。所々赤い光を称えた黒い魔力、
それが無造作に開いた手の形を取ったのが魔法『黒の手』。それはアッシュの集中に合わせて二つ三つ四つと増え、先頭のマモノがアッシュ
に拳を振り下ろそうとする直前、ゴ、と重苦しい音を伴って一気にマモノ達を薙ぎ払った。兄の前で揺らめいていた何体ものマモノが、
その一撃だけで倒れる。
「フン…悪かねえな。これが『黒の書』の力、魔法か」
「私の授けた力、早速使いこなすとは…さすガッ」
「ああ、悪い」
構えを変えようと鉄パイプを振るった拍子に、その先が『黒の書』の顔面、表紙の装丁に描かれた顔のまさに顔面にゴンと突き当たった。
「…」
店の外、当時は駐車場だったであろう塩の雪に埋め尽くされた広場には、まだマモノが蠢いている。だが相当距離がある。その余裕で
じっと『黒の書』を振り返り眺めたアッシュは、はぁ、とひとつ呆れたようなため息を零した。
「…ヴァン…お前な、ぼーっと浮いてねえで避けろ」
「………………」
本というのは何と不便な身なのだ、と半泣きで呟くヴァンを放置して、アッシュはマモノの殲滅に戻った。黒の手の次は黒の弾、更に
黒の処刑、黒の槍。次々と順当に魔法を会得しては使いこなし、鉄パイプでの攻撃と合わせてどんどんマモノを倒していく。ダメ押しと
ばかりに現れた巨大なマモノにも臆せず立ち向かい、アタックゲージの撃破も難なくこなした。舞台裏ではさすがアッシュだとルークが
拍手しガイが感心していた鮮やかさである。
「フン」
鉄パイプを構え直し、周囲を見渡す。一時はマモノで埋め尽くされていた周囲は、すっかり元の静寂を取り戻していた。音も無く雪が
降り積もる、空恐ろしい静寂を。
今の内に倉庫まで。駆け出そうとした足を止めたのは、激しく咳き込む妹の声だった。
「!? ナタリア!?」
駆け出した兄が向かったのは倉庫ではなく、妹の元。座り込んだ体勢で床に手をつき、もう片方の手で口元を覆って咳き込んでいる。
兄は大丈夫かと声を掛けながら背中をさすってやる。
「……もう、大丈夫ですわ…。ごめんなさい、お兄様」
「気にするなと言っているだろう。…本当にもういいのか」
「ええ…。………わたくしが、咳き込んでばかりいては……あのまっ黒なおばけが、また現れるのでしょうか…?」
「心配するな。あんなものは俺がすぐに片付けてやる」
自信に満ちた表情で不敵に笑って見せると、妹は安心したようにほっと息をついた。
「…ありがとう、お兄様…。ねえ、御覧になって。わたくし、こんなものを見つけましたの。半分こしましょう?」
弱弱しく顔を上げ気丈にも笑顔を見せるナタリア。彼女が差し出したのはクッキーで、懐には何か缶のようなものがちらりと覗いた。
それを見た途端ぎょっとしたのは、何故か取り出した張本人。
「っまあ! チキンサンドと紅茶と交換するように言ったではありませんか、何故またクッキーが出てきますの!?」
キッと睨んだ先には『黒の書』。先ほどアッシュに魔法を授けたものとは別の、彼女の傍らにあった分だ。
「このシーンはクッキーとト書きがあるのだ、勝手に変えるわけにもゆくまい。第一、台本にないのだから用意されておらぬだろう」
「そういうのを四角四面といいますのよ、もっと柔軟に事に対応しなければ! よろしいですか、もう一度言いますわよ! 折角なのです
からアッシュの好物のチキンサンド、それに食べ物だけでは喉に詰まってしまいますからティーセットもですわ! 早くなさい」
「なさいと仰られても、ない小道具は出せぬのですよ、王女殿下」
「わたくしは病弱設定で容易に動けませんのよ!! アッシュは主役ですから論外、その分おまえが動かずに誰が動くのです! まったく、
大きな口を叩く割に使えませんわね!」
ぐっさり。
『黒の書』の直上から包丁が落下してきて刺さったように見えたのは、気のせいだろうか。
「そういやヴァン、てめえやけに静かだと思ったらこっちの『黒の書』に意識を移動させてたのか。まあ戦闘に集中できて助かったがな」
「…魔法の力を授けたのは誰だと思っているのだ…。そうだアッシュ、お前からも王女に一言」
「折角のナタリアの気遣いを無碍にしやがって。チキンサンドくらい控え待ちしてる連中に作らせればいいだろう。熟練度は充分足りてる
はずだ。紅茶もついでに淹れればいい」
簡単なことじゃねえか、とさらりと返され、絶句の後またもやしくしくと泣き出す『黒の書』。
「…こんな廃墟からいきなりチキンサンドと暖かな紅茶が出てきては不自然だと、普通に考えれば分かるだろう…。そんなものがあるの
なら、食料を探しに外へなど、出る必要はないではないか…」
「まあ、細かいことをブツブツと。女々しい本ですこと…っ、ゴホゴホッ、ゴホッ!!」
「ナタリア!?」
咳き込み体を丸めて縮こまるナタリア。その拍子にクッキーが落ちてしまったが、アッシュは構わず抱き寄せた。背中をさすってやるが、
今回は一行に落ち着く様子がない。
「ナタリア、しっかりしろ!」
「ごめん、なさい…クッキー、落としてしまいましたわ…、ゴホッ!!」
「喋らなくていい、ナタリア!」
「お兄様…お願いです。体の弱いナタリアのことを、嫌いにならないで……」
兄を硬直させたのは、妹の涙でも、その健気さに胸を打たれたからでもない。
一生懸命に謝る妹の防寒着と肌の間から、黒い靄が立ち上ってきたからだ。靄はどんどん濃くなって溢れてくる。異変はそれだけではない。
胸元から首、顎、頬へ、まるで蛇が這うようにうぞうぞと、音も無く妹の肌の上を伝ってくる黒い天使文字。
防寒着はきっちりと着込んでいるのに、ぞく、と背筋が凍る。その靄も文字も、兄が最も恐れていたもの。
一瞬『黒の書』へ視線を落とす兄。触ってしまったのか。妹は、これに。―――駄目だと念を押したのに!!
兄の苦悶など構わず、驚くほど性急に妹の体力は奪われていき、呼吸が浅く速くなる。
「ナタリア! ナタリア、しっかりしろ!!」
「………お兄…様……………大好き…です……」
「ナタリア!! ナタリア、目を閉じるな!! ナタリア!!」
つ、と妹の頬を涙が伝い、瞼が下りた。
「ナタリア!!!」
悲痛な叫びを上げながら、その体を抱き締める兄。くそっと悪態をつきながら、拳を床に打ち付ける。
「誰か…誰でもいい、誰か…!! 俺はどうなってもいい! ナタリアを助けろ!!!」
雪が降る。
ただ静かに、雪だけが降り積もってゆく。
それは遺灰。それは遺体。かつて人間であったモノの成れの果てである塩の雪。
五十年前に赤き竜を串刺しにして絶命たらしめた凶刃、東京タワー。
亡骸はとっくに撤去され、今やただ鉄骨を組み上げただけのモノとなり果てた塔。
その足元で、少年は叫ぶ。
絶叫を汲み上げたのは――――――――――
UPの際の海原のツブヤキ…興味のある方は↓反転して下さい(大した事書いてません)
シリアスなんだかギャグなんだかダークなんだかコメディなんだかよくわからん感じで。