 |
|
ハナハマセンブリとベニバナセンブリの大きな識別点の1つが、
花の時期の根生葉とされています。
「ハナハマセンブリは花の時期には根生葉はロゼットを形成しない」と
図鑑に書いてありますが、根生葉が見られるものが各地で報告されています。
私も昨年までは、花期に根生葉が見られないものがハナハマセンブリだと
思っていましたが、どうもそうではないようです。
そこで、この根生葉について調べてみることにしました。
根生葉・・・根から生じているように見える葉のことで、
正確には地上茎の基部の節につく葉のこと。
(植物用語辞典 清水建美 著より) |
| ベニバナセンブリの根生葉 |
|
|
昨年の夏に種子を蒔いていたハナハマセンブリが、今年(2006年)の春に発芽しましたので、葉を観察してみました。
1. 4月23日
|
2. 5月10日
|
3. 6月24日
この時期には花を咲かせています。
|
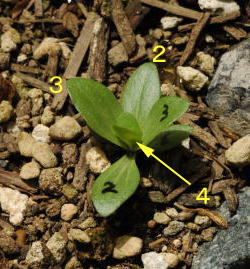
|
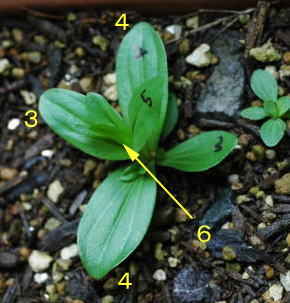 |
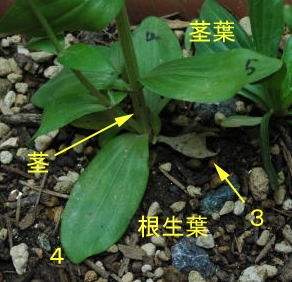 |
発芽した葉に順に番号をつけました。
1.2.3番目の葉まで出ました。
4番目が出始めています。
1番の葉は3番目の葉の下に
少し見えています。 |
手前の大きな葉は4番目の葉です。
5番目の葉が出ました。
6番目の葉が出始めています。
1.2番は3.4番目の葉に
隠れています。 |
4番と5番目の葉の間には
茎が伸びています。
1.2番目の葉はすでに枯れました。
3番目の葉も枯れ始めています。
|
観察したことから、1〜4番目の葉は基部の節についていますので、根生葉です。
5番目から上の葉は、茎の節間がのびて、茎についていますので茎葉になります。
根生葉は花の咲く時期の頃までに、徐々に枯れてゆきますが、4番目の葉のように、花期にも残っているものもあります。
2. フィールドでのハナハマセンブリの根生葉
フィールドでのハナハマセンブリも同時に観察してみました。 4月〜花が咲くまでは、根生葉がはっきりと確認できます。
| 4月18日 |
|
5月20日 |

発芽して約1ヶ月頃
|
|

茎がのび始めました 根生葉と茎葉が見られます
|
| 6月1日 |

茎葉に比べて大きな根生葉が確認できます |
A. 6月18日に花が咲き始めた株です、このハナハマセンブリには まだはっきりと根生葉が見られました。
違う場所に咲いていた花の時期のハナハマセンブリです。 少し枯れかけていますが根生葉が見られます。 (6月25日)
B. こちらは根生葉が枯れていった株の様子(画像1.2)と、 枯れていっていることがはっきりわかる根生葉(7月1日)です。
| 1. 6月13日 |
→ |
2. 6月25日
左と同じ個体です |
|
7月1日
違う場所でのハナハマセンブリ |

根生葉と茎葉が見られます |
→ |

根生葉と1番下の茎葉は
枯れてしまいました |
|
.jpg)
枯れてしまっていますが
大きな根生葉が見られます。
|
今年(2006年) 観察したことをまとめてみると、
私の周りでみられるハナハマセンブリの根生葉は、発芽して花が咲く頃(6月頃)まではちゃんとありますが、
徐々に枯れていって、花の時期の中〜後半になると、多くの株では根生葉が見られなくなるようでした。
しかし、A.のように生育環境などによっては、花の時期にも根生葉がはっきり見られるものも見つかりました。
( 2006.7.13 )

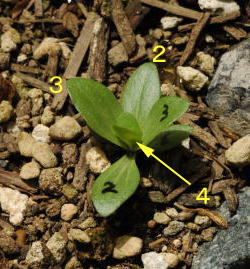
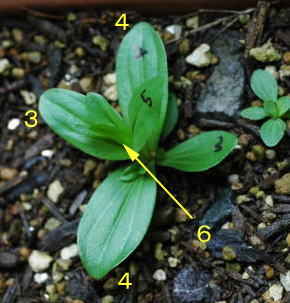
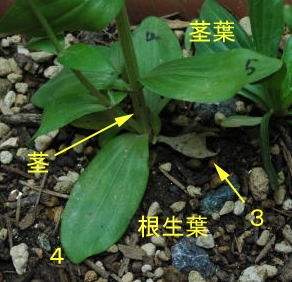









.jpg)